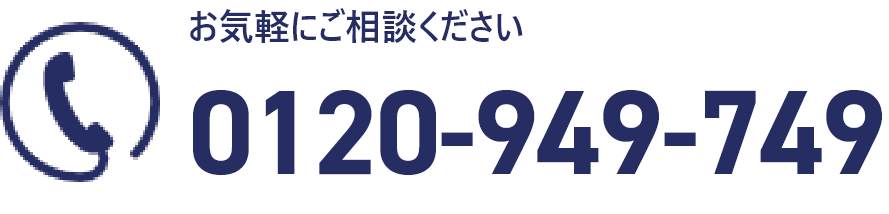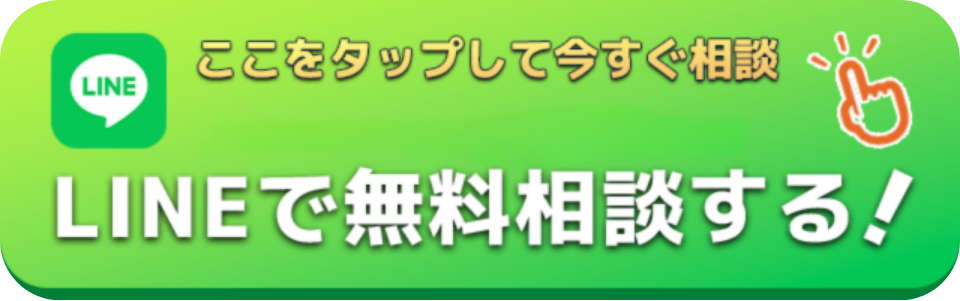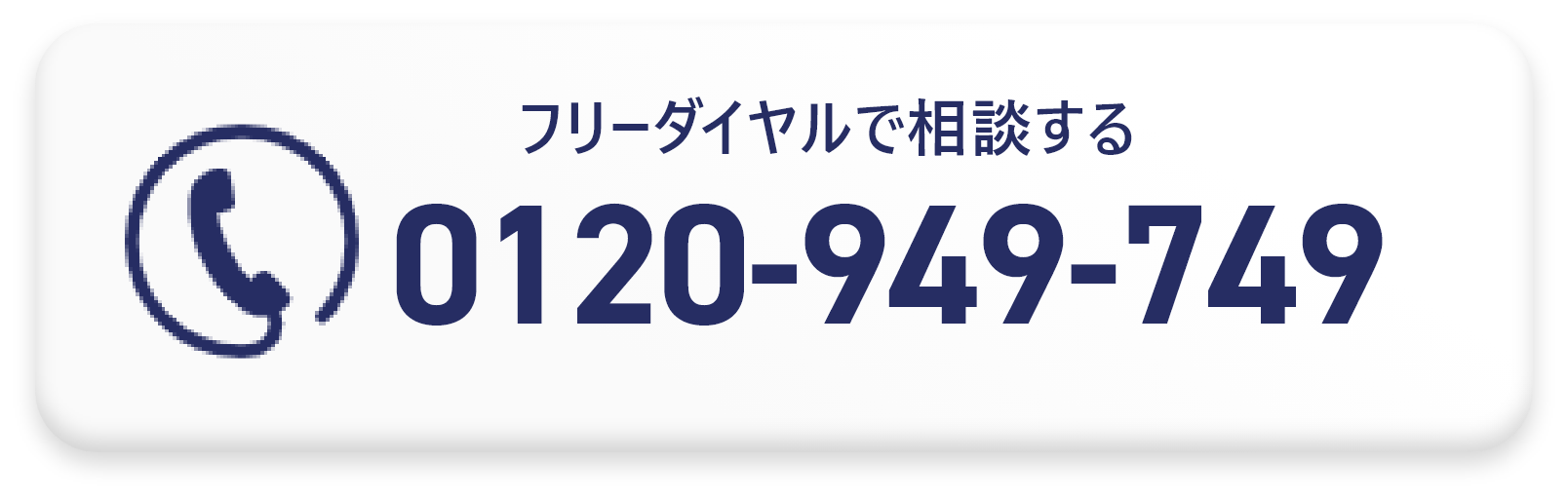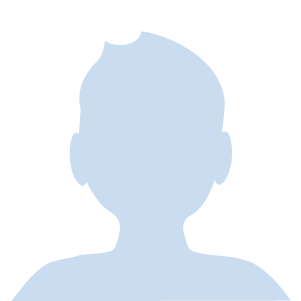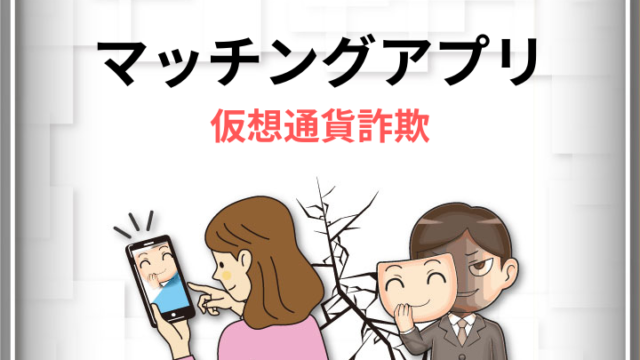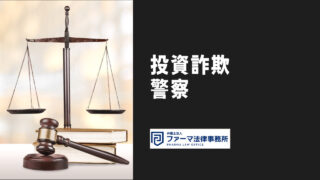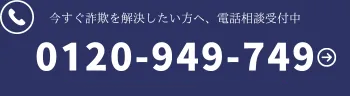仮想通貨詐欺と呼ばれるコインの一覧は以下の通りです。
仮想通貨による投資は、少額から始められるため投資初心者から高い利益を求めるベテラン投資家まで広く人気がある投資のひとつです。
その反面、偽の仮想通貨の購入や投資サイトへの入金を誘導してお金を騙し取る「仮想通貨詐欺」の被害に遭う人も増えています。
全国の消費生活センター等には暗号資産(仮想通貨)に関する相談が多数寄せられており、2021年度の相談件数は6,350件になっています(注)。国民生活センターでは、これまでも暗号資産に関する高齢者の契約トラブルや、実態不明な投資話への注意喚起を行ってきましたが、最近の相談事例をみると「SNSやマッチングアプリで知り合った相手に勧誘されて送金したが、出金できなくなった」など、SNSやマッチングアプリをきっかけとしたトラブルが目立っています。また、友人や知人から「暗号資産でもうかる。人を紹介すれば紹介料も入る」と勧誘されお金を預けたが、出金できない、返金されないといったケースもみられます。
仮想通貨による詐欺にはさまざまな手口がありますが、その一つとして「詐欺コイン」と呼ばれる資金を集めるために作られた未公開のコイン(仮想通貨)を売りつけ、資金を騙し取る詐欺があります。
当記事では以下のような内容を紹介します。
【詐欺被害の疑いがある方へ】
詐欺被害の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士への無料相談が可能。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら
\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。
仮想通貨詐欺と呼ばれるコイン一覧-実際の事例をもとに徹底解説-
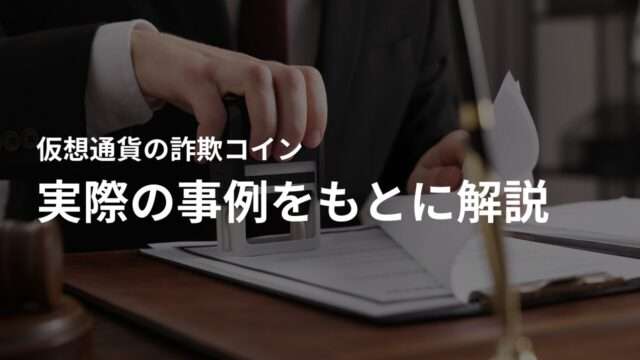
仮想通貨詐欺コインの一覧は以下になります。
仮想通貨詐欺があちこちで注意喚起されていることから勘違いされがちですが、仮想通貨自体は詐欺ではありません。
しかし「必ず儲かる」、「毎月20%の高利率の返還が受けられる」などと甘い言葉で誘って、実際には公開しないコインを売る詐欺は過去に数多く存在しています。

被害を未然に防ぐためには、過去の詐欺事例とその手口を知ることが重要です。
ここでは、これまでに報告された主な詐欺コインの実例を解説します。
TLCコイン:上場しておらず価値は0
TLCコインは2015年頃からクラブスパークル社によって販売され、「次世代のビットコイン」と宣伝されていました。
しかし、このコインは一度も正規の取引所に上場されることなく、実質的な価値は0円と言われています。
投資者は何年にもわたって換金できない状態が続き、多くの人々が資金を失う結果となりました。
仮想通貨が正規の取引所に上場していないケースでは、換金の手段がなく詐欺的である可能性が極めて高いと考えるべきです。
このケースからは、いかに魅力的な宣伝文句があっても、実際に流通する仕組みがない仮想通貨には手を出すべきでないことが分かります。
サークルコイン:実態がない会社の仮想通貨
サークルコインは合同会社エクラドクールが販売していた仮想通貨で、発行元を架空の米国法人と偽って販売されていました。
東京国税局などの税務調査により、同社が2年間で約9億円の所得を隠していたという脱税問題も発覚しています。
実態は都内の企業がコインを作り、発行元情報を偽っていたという典型的な詐欺事例です。
海外の企業を発行元と謳いながら実態が不明確な場合は、情報の真偽を確認することが重要です。
このケースでは被害者による集団訴訟も進められており、多くの投資家が被害を受けたことが窺えます。
ノアコイン:過去に虚偽の誇大広告を行った
ノアコインは「フィリピン政府公認」を謳い文句に多くの資金を集めましたが、2018年に在日フィリピン大使館がその関与を正式に否定しました。
フィリピン政府当局からも警告を受け、ノア財団はプロジェクトを一時停止せざるを得なくなりました。
政府機関との提携を偽る手法は詐欺コインによく見られる典型的な手口です。
政府機関の公認や協力をうたう場合は、必ず公式情報源から確認を取ることが被害防止につながります。
投資家への返金問題も発生し、多くの人々が資金を回収できない状況に陥りました。
クローバーコイン:ネズミ講詐欺
クローバーコインは48ホールディングス株式会社が高配当を謳った連鎖販売取引(マルチ商法)の手法で勧誘していた仮想通貨です。
2017年10月に消費者庁が同社に対して業務停止命令を出し、その後販売終了となりました。
勧誘時に「必ず値上がりする」などと虚偽の説明をしていたことが特定商取引法違反として認定されています。
友人や知人からの紹介でマルチ商法的に勧誘される仮想通貨は、詐欺的である可能性が高く注意が必要です。
このようなマルチ型の仮想通貨詐欺は、知人間の信頼関係を利用するため特に注意が必要です。
参考:消費者庁
ジュエルコイン:詐欺セミナーにて販売
ジュエルコインはザンビアのアクアマリン鉱山など宝石の価値に裏付けされていると宣伝されていましたが、実際にはその実態は確認されていません。
紹介者に報酬が入るネットワークビジネスの形態を取り、大々的なセミナーで販売されていました。
後に運営企業の代表者らが別件の投資詐欺容疑で逮捕されるなど、信頼性の欠如が明らかになっています。
実物資産による価値の裏付けを謳う仮想通貨は、その資産の存在証明が不可欠です。証明できない場合は詐欺の可能性が高いでしょう。
物理的資産を担保にするという謳い文句は魅力的に聞こえますが、その検証が困難なことが多いため警戒が必要です。
参考:StartHome
ワンコイン:世界的規模のポンジ・スキーム
ワンコイン(OneCoin)は世界的に巨額の資金を集めたポンジ・スキーム型の詐欺で、米FBIが創始者を「史上最大級のマルチ商法事件の首謀者」として指名手配しています。
暗号資産業界で最大級の詐欺事件として各国で捜査・起訴され、日本国内でもセミナー勧誘による被害が報告されています。
関与者が逮捕された例もあり、国際的な詐欺コインの典型例として知られています。
高利回りを約束する国際的な仮想通貨プロジェクトでは、特に公的機関からの警告がないか確認することが重要です。
このケースは、詐欺的な仮想通貨が国境を越えて被害を拡大させる危険性を示しています。
参考:Bloomberg
エターナルコイン:資金流用と規制問題
エターナルコイン(XEC)は利用者資産の一時流用など資金決済法違反により、規制当局から業務停止命令を受けた事例です。
2018年4月、関東財務局はエターナルリンク社に対し、顧客預かり金を経費に充当していたことやマネロン対策の不備を理由に処分を下しました。
その後、日本で唯一取り扱っていた事業者が金融庁への交換業者登録を断念し、日本市場から撤退しています。
仮想通貨取引業者の監督官庁からの処分歴は、その事業者の信頼性を判断する重要な指標となります。
結果として、エターナルコインは日本で換金不能となり、実質的な被害が生じました。
参考:Reuters
ディールコイン:技術的実態のない詐欺
ディールコインは「中東の産油国の要望で作られた」と説明されましたが、ブロックチェーンを使わず単なるHTMLデータで構成されていた驚くべき詐欺事例です。
公式サイトは閉鎖され運営者も逃亡し、日本でも多数の出資者が被害に遭ったとみられています。
被害総額は噂で100億円を超えるとも言われる大規模な詐欺案件でした。
仮想通貨の技術的基盤が不明確である場合は、専門家の意見を参考にするなど慎重な判断が必要です。
このケースでは、基本的な技術的検証さえ行えば詐欺を見抜くことができた可能性があります。
リコイン:不動産担保の虚偽宣伝
リコイン(REcoin)は「不動産で担保された仮想通貨」という謳い文句で投資を募りましたが、実際には裏付け資産は存在しませんでした。
2017年、米国でこのICOプロジェクトを運営していた実業家が詐欺容疑で逮捕・起訴されています。
約3000万円以上を投資家からだまし取ったとされ、米証券取引委員会(SEC)も初期の詐欺的ICO事例として摘発しました。
資産裏付け型を謳う仮想通貨では、その資産の実在性や法的な裏付けを独立した第三者機関が確認できるかが重要なポイントです。
日本の金融当局も類似案件に注意を呼びかけており、国際的な詐欺事例として認識されています。
\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。
仮想通貨の詐欺コインの主な特徴7選
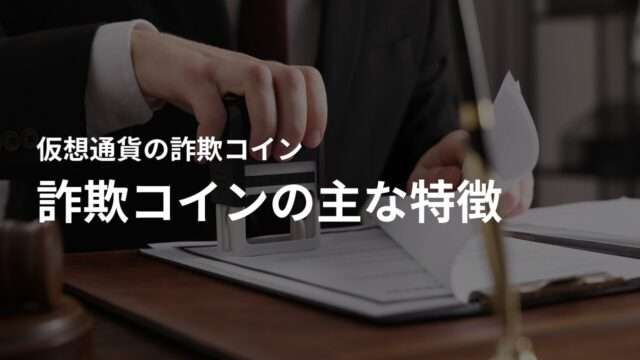
暗号資産投資における詐欺被害を防ぐためには、怪しいコインの特徴を事前に知っておくことが重要です。
詐欺コインには共通する特徴があり、これらを理解することで危険な投資案件を見分けることができます。
正規の暗号資産と詐欺コインの違いを知り、適切な判断ができるようになりましょう。
ここでは、詐欺コインに共通する危険な特徴について解説します。
正規取引所での取り扱いがない
詐欺コインの最も明確な特徴は、金融庁登録済みの正規取引所で扱われていないという点です。
一般的な暗号資産は世界中の取引所で自由に取引されていますが、詐欺コインは「限定販売」や「先行販売」といった言葉で特別感を演出します。
本来、真に価値のある暗号資産は広く市場に流通し、複数の取引所で購入可能なはずです。
「特定の場所でしか購入できない」というのは不自然な状況であり、これは詐欺コインを見分ける重要なサインとなります。
正規の暗号資産ならば、金融庁に登録された取引所で自由に売買できるのが基本です。
不自然に高い最低購入額
通常の暗号資産は数百円程度から少額で購入可能ですが、詐欺コインでは「最低10万円から」などと不自然に高額な購入額を設定していることがよくあります。
これは、「高額を支払ったのだから取り戻したい」「失いたくない」という心理(サンクコスト効果)を狙い、被害者が途中でやめにくくなるよう設計されている可能性があります。
正規の取引所であれば、ビットコインでも500円程度から購入できるのが一般的です。
不自然に高い最低購入額の設定は、詐欺師が一回の取引でより多くの資金を詐取しようとする意図の表れです。
少額からの投資ができない仕組みは、消費者保護の観点からも問題があります。
価格・買取保証の虚偽の安心感
「価格保証」や「買取保証」を謳う暗号資産は極めて怪しいと考えるべきです。
暗号資産の価格は市場原理で変動するものであり、事前に価格や買取を保証することはできません。
実際には価値のないコインを販売し、一部だけ返金することで詐欺師は十分な利益を得ています。
市場価格が変動する暗号資産において、将来の価格を保証するというのは経済原理に反する非現実的な約束です。
正規の暗号資産投資では、価格変動リスクは投資家自身が負うものであり、これは金融商品の基本原則です。
セミナーによる勧誘と紹介料システム
暗号資産のセミナーでの勧誘は、多くの場合マルチ商法やネズミ講の手法を用いています。
紹介者に高額な紹介料が入る仕組みが組み込まれており、「絶対に値上がりする」などと断言する勧誘手法は詐欺の典型的な特徴です。
本当に価値のある暗号資産なら、このような限定的な販売方法を取る必要はありません。
新規参加者の勧誘に対して高い報酬を設定するシステムは、商品自体の価値ではなく、会員拡大による利益を目的としている可能性が高いです。
正規の暗号資産は、その技術的価値や市場での評価によって価格が決まるものです。
代理店による販売と特別感の演出
「唯一の正規代理店」「独占契約」などと称して販売される暗号資産も危険信号です。
現代の暗号資産はオンライン取引所で直接購入できるのが基本で、わざわざ代理店を介す必要はありません。
さらに代理店になれば高い仲介料が得られるといった勧誘もマルチ商法の特徴です。
特定の代理店でしか購入できないという制限は、透明性の低さを示す重要なサインであり、詐欺的なビジネスモデルを疑うべき要素です。
正規の暗号資産取引は、透明性の高いオープンな市場で行われるものです。
著名人の名前を無断使用した宣伝
「有名人が購入している」「著名人がバックについている」といった宣伝文句も詐欺の典型的な手法です。
詐欺師は一般人が真偽を確認できないことを利用して、著名人の名前を無断で使用します。
多くの場合、著名人自身も名前を使われていることを知らず、被害者となっています。
著名人の関与を主張する場合は、その真偽を公式情報から確認することが重要です。SNSや公式サイトで発表されていない情報は疑ってかかるべきでしょう。
信頼性の高い暗号資産プロジェクトは、透明性のある情報開示と技術的価値に基づいて評価されるものです。
ICOにも注意
ICO(イニシャル・コイン・オファリング)とは、企業が独自のトークンを発行して資金調達する方法です。
このトークンは「デジタル引換券」のような役割を果たし、既存のブロックチェーン基盤を利用して作られます。
投資家はこれらのトークンを比較的低価格で購入し、企業は集めた資金で事業開発を行います。
近年、ICOを装った詐欺行為が世界的に急増しており、投資家は細心の注意が必要です。
世界各国での暗号資産に関する法規制はまだ発展途上であり、投資家への法的保護が十分とは言えません。
安全な投資を心がけるなら、プロジェクトチームの経歴や実績、ホワイトペーパーの内容を確認し、怪しいと感じるものには投資を控えることが賢明です。
\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。
仮想通貨詐欺の兆候とは?見抜くための注意点

仮想通貨投資においては、詐欺の手口を事前に知ることが自己防衛につながります。
巧妙化する詐欺から身を守るために、警戒すべき兆候を理解しておく必要があります。
詐欺師は人々の「簡単に儲けたい」という心理を突いてきますが、冷静な判断ができれば被害を防げる可能性が高まります。
ここでは、仮想通貨詐欺を見抜くための主な警告サインについて解説します。
リターンを保証する
「必ず儲かる」「〇%の利益が確実」といった将来のリターンを断言する表現には注意が必要です。
仮想通貨を含む投資商品は価格変動リスクを伴うため、将来の収益を保証することは不可能です。
金融の基本原則として、高いリターンには高いリスクが伴うことを忘れてはいけません。
確実な利益を約束するプロジェクトは、詐欺の可能性が極めて高いと考えるべきです。
運営チームの詳細が不明
信頼できる仮想通貨プロジェクトでは、運営チームのメンバー情報が公開されているのが一般的です。
経歴や実績が確認できる開発者やアドバイザーの存在は、プロジェクトの信頼性を示す重要な指標となります。
匿名の開発者が存在する正当なプロジェクトもありますが、運営全体が不透明な場合は注意が必要です。
運営者の情報が不明確であったり、経歴を確認できなかったりする場合は、詐欺の可能性を考慮すべきです。
ホワイトペーパーなどが存在しない
正規の仮想通貨プロジェクトには詳細なホワイトペーパーが必ず存在します。
ホワイトペーパーとは、その仮想通貨の技術的仕組み、目的、実現方法などを詳しく説明した文書です。
信頼できるプロジェクトのホワイトペーパーは、専門家でなくても理解できる説明と、技術的な裏付けを両立させています。
ホワイトペーパーが存在しない、または内容が曖昧で具体性に欠ける場合は、プロジェクトの信頼性を疑うべきです。
宣伝活動が過激すぎる
詐欺的なプロジェクトほど派手な宣伝活動に力を入れる傾向があります。
有名人やインフルエンサーを起用した広告、SNSでの積極的な宣伝、大規模なオフラインイベントなどが特徴です。
これは短期間で多くの投資家から資金を集め、素早く姿を消すための戦略です。
根拠不明な利益を強調するマーケティングに惑わされず、冷静にプロジェクトの実態を確認することが重要です。
完全無料や無リスクを謳う
「完全無料」「リスクゼロ」などの非現実的な条件を提示するプロジェクトには警戒が必要です。
現金でも仮想通貨でも、投資には必ずリスクが伴うものであり、完全な無料やリスクゼロを約束する投資話は現実的ではありません。
「フリーマネー」のような甘い言葉に惑わされないことが大切です。
「無料で参加できる」「リスクなしで利益を得られる」といった謳い文句は、詐欺の典型的な誘い文句です。
仮想通貨詐欺に引っかからないために!4つの予防策
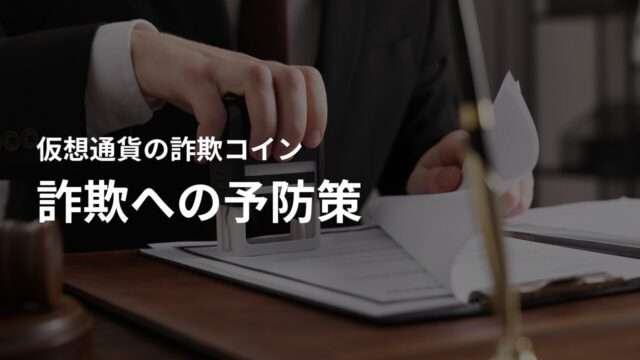
仮想通貨詐欺の特徴は以下の通りです。
仮想通貨はそもそも国や銀行によって発行されている法定通貨ではありません。
裏付けとなる資産がないことや購入後の社会情勢などのさまざまな要因によって価格が大きく変動する可能性があります。
ただ、仮想通貨そのものや価格の変動においては詐欺とは言えません。
ここでは仮想通貨を利用したお金集めが目的の、意図的な仮想通貨詐欺の特徴について解説します。
仮想通貨の儲け話やセミナーには十分注意する
仮想通貨の儲け話やセミナーには十分注意してください。
仮想通貨は一般的な認知度は増えてきたものの、まだまだ成長段階で仕組みについて詳しく知っているという人は少ないため、嘘の情報に惑わされる可能性があります。
特に仮想通貨や投資の初心者は「早く知識を身につけたい」という思いから、「人数限定の有力な情報」や「今買わないと後悔する」などの煽り文句に引かれてしまうかもしれません。
しかし、儲け話やセミナーには詐欺の危険がありますので、以下のような場合は十分注意しましょう。
- 講師のプロフィールが曖昧で参加費が高いセミナー
- 聞いたことのない仮想通貨の直接購入の誘い
- 「絶対に儲かる」「還元保証がある」など、損失がないと謳っている
仮想通貨に「絶対儲かる」方法は存在しませんので、どんなに甘い言葉を並べられても信じないことが大切です。
有名人の名前を使った宣伝や誇大広告を注意する
有名人の名前を使った宣伝や誇大広告を注意してください。
仮想通貨詐欺に限らず、有名人の名前を宣伝に利用して集客し商品の信頼性を高める詐欺の手法は昔からよく見られます。
「有名人Xはこのコインで儲かった」「〇〇がおすすめする今買うべきコイン」などと、あたかも有名人が関わっているように見せかけた偽の情報や、事実に反する誇大広告には注意が必要です。
実際に有名人が発信している動画やSNSなどの一部を勝手に流用し、偽の投資サイトに入金させるように誘導する手口も多く見られます。
ぱっと見本物のように巧妙に作られていることが特徴ですが、外部からあらためて検索すると事実ではないとわかるケースがほとんどです。
重要なのは、その場の情報を鵜呑みにして決断せずに慎重になることだと言えるでしょう。
紹介者からのみの購入や取引所への送金はしない
紹介者からのみの購入や特定の取引所への送金はしないようにしてください。
初心者が仮想通貨詐欺被害に遭う手口で多いのが、紹介者にお金を渡して購入する方法です。
近年増えているのが、マッチングアプリで勧誘されて偽サイトへ入金して出金できなくなるケースです。
サイト上で利益が出ているよう見せかけ追加でどんどん入金させ、いざ出金したいと申し出ると税金として数十万以上のお金を要求されたり、紹介者が消息を絶ち全く連絡が取れなくなったりします。
これらの手口で、マッチングアプリ利用者の増加に伴い被害が急増し問題になっています。
日本での仮想通貨の購入は仮想通貨取引所を介するのが一般的で、取引所の運営は金融庁への暗号資産交換業者登録が必要です。
原則は国内取引所の利用に限られているため、詐欺に遭わないように仮想通貨取引するためには金融庁に登録されている取引所で購入するのが望ましいでしょう。
無料配布している仮想通貨コインに騙されない
無料配布している仮想通貨コインに騙されないようにしてください。
仮想通貨の流通の中には「エアドロップ」という、まだ有名になっていないコインを無料配布して認知度を上げ、そのコインの流通量を増やす方法がとられることがあります。
エアドロップ自体は価値が未知数のコインを無料で流通させるため詐欺ではありませんし、うまく運用して将来的にそのコインの価値が上がれば大きな利益になります。
しかし、エアドロップを利用した詐欺被害も増えているため、「無料配布」という言葉に踊らされて個人情報やウォレットの情報を知られないように注意が必要です。
例えば、コイン配布の際に「プライベートキー」や「パスワード」の提示を求められる場合は詐欺の可能性が高いため、申し込まないようにしましょう。
また、メールアドレスやパスワードの使い回しによる情報の盗用の危険もあるため、メインのアドレスとは別のアドレスを利用したり、パスワードは都度変更するなどの対策をとることをおすすめします。
\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。
仮想通貨詐欺で騙されたらどうする?解決に向かう対処法3選
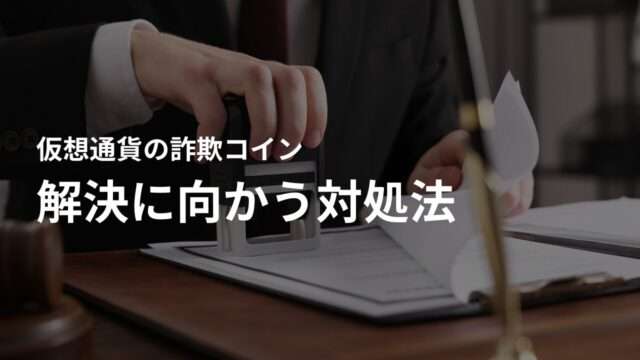
仮想通貨詐欺で騙された場合の対処法は以下の3つです。
「自分は騙されない」と思っていても、万が一仮想通貨詐欺被害に遭ってしまったらなるべく早く対処することが大切です。
詐欺犯はお金を手に入れたらすぐに行方をくらまして逃げる手段に長けていますので、騙し取られたお金が返金される可能性は非常に低いと言われています。
そのため自分で解決しようと時間を浪費するよりも、一刻も早い解決のために専門の窓口や以下の相談先に助けを求めましょう。
仮想通貨詐欺専門の弁護士に相談する
仮想通貨詐欺被害に遭ってしまったときは、仮想通貨詐欺専門の弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は被害者の代理人として返金請求や損害賠償請求など、被害回復のために法的措置が取れる相談先です。
中でも仮想通貨専門の弁護士であれば、過去事例に精通しているため似たケースから解決法を見つけられる可能性がありますし、海外の仮想通貨取引所とのやり取りを請け負ってくれる可能性もあります。
消費者サービスや金融庁などに相談する
仮想通貨詐欺の被害件数急増に対し、金融庁や消費者庁などによる駅の張り紙や街頭ポスターなどの注意喚起を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
金融庁による「金融サービス利用者相談室」や消費者センターの「消費者ホットライン」では相談員に電話で直接話を聞いてもらえます。
情報の整理や今からやるべき行動に関するアドバイスが受けられることができます。
仮想通貨詐欺で騙されてしまったときに取るべき行動がわからないときには積極的に利用し、今できることを始められるようにしましょう。
友人と家族など第3者に相談する
「詐欺に遭ってしまったかもしれない」と状況が不確定な段階では、まず自分の置かれている状況を第三者に客観的に見てもらうことが大切です。
そのためには信頼できる友人や家族に詳細を話して客観的な意見を聞きましょう。
第三者に詳細を説明すると、それまで信じていた内容が怪しく思えたり現実的にありえないと気づくこともあります.
また、友人や家族はお金の利害なしにあなたのことを心から心配して意見してくれるでしょうから、貴重な意見だと思えるはずです。
そして第三者の目から見て、明らかにお金を騙し取る目的だと判断されたら弁護士など専門の窓口に相談して解決に向かうことをおすすめします。
\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。
仮想通貨詐欺コインの一覧のよくある質問
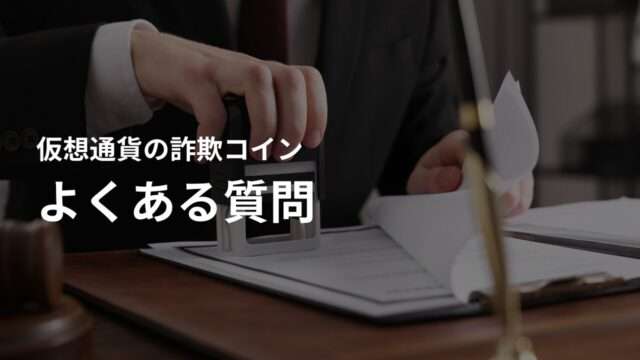
仮想通貨詐欺コイン一覧についてよくある質問を以下のようにまとめました。
仮想通貨自体が詐欺ではないとわかっても、いざ始めるときに詐欺に関して不安があるかもしれません。
普段感じた疑問を解決していきましょう。
仮想通貨詐欺でよくある詐欺手口とは?
仮想通貨詐欺に見られるよくある手口には以下のような特徴が挙げられます。
- 価格保証や買取保証がある
- セミナーや代理店など金融庁登録取引所以外で買付する
- 仮想通貨の購入単価が異様に高い
- 有名人の名前が宣伝広告に使用されている
仮想通貨は価格変動型の金融商品に分類されますので、価格に保証がつくことはありません。
購入先も日本においては金融庁に登録された仮想通貨取引所が一般的であり、海外の取引所や未登録の取引所での購入は自己責任になります。
仮想通貨詐欺では、「絶対損しない」「この有名人が儲かったから今買うべき」など根拠のない儲け話をあたかも本当のように見せかけてくる手口が特徴です。
「仮想通貨に絶対はない」、「自分と他人は違う」ということを常に念頭に置くようにしましょう。

マッチングアプリから仮想通貨詐欺に発展するケースが多いって本当?
近年のコロナ化の影響で、マッチングアプリの利用者が急増しています。
結婚相手や恋人探しはもちろん、友人や共通の趣味仲間集めにも利用されており、出会いのツールとして定着されつつありますが、仮想通貨詐欺のターゲット探しに利用されることがあるようです。
仮想通貨・FXの海外取引サイトへの入金を要求してくる手口で、マッチングアプリで出会って恋愛関係になってから「将来のために投資しよう」などと結婚を餌にお金を騙し取る「国際ロマンス詐欺」や「結婚詐欺」の一環となるケースが多いようです。
マッチングアプリからの投資先は偽物の投資サイトであることがほとんどですので、話を持ちかけられたらサイトの実態をしっかり調べることをおすすめします。
【事例】実際に仮想通貨詐欺に遭った人はいる?
残念ながら仮想通貨詐欺に実際に遭ってしまった人は存在します。
コインを利用してきた仮想通貨をよくやった人は自分が詐欺にあうとは考えたことないでしょう。ただ、一瞬の勘違いや判断ミスで仮想通貨詐欺に遭う可能性はあります。
同署によると、男性は昨年11月ごろ、何者かからフェイスブックを通じて連絡を受け、暗号資産(仮想通貨)「イーサリアム」を紹介されたという。偽のインターネットサイトに誘導され、今年2月から7月までの間、35回にわたり計約1200万円を送金した。
以上のニュースによると、「イーサリアム」という仮想通貨を紹介され、5ヶ月間で約1200万円を騙し取られたようです。
他にもSNSやネットなどで仮想通貨詐欺に遭ってしまった実例を簡単に調べられます。
また、英国でも偽の広告を利用して仮想通貨詐欺を行っていることが増えていると言われています。
「自分はプロだから大丈夫」と言いながら安心して大きな金額をコインに使うことは大変危険な行動です。
仮想通貨詐欺に遭わないために、冷静に考えて行うようにしてください
\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。
まとめ:詐欺コインの特徴を知って、怪しいと感知できるようになろう!
- 詐欺コインの実際の事例6例
- 仮想通貨詐欺の4つの特徴
- 仮想通貨詐欺被害に遭った場合の対処法
仮想通貨の詐欺コインには、これから価値が出る可能性がある新しいコインを集金目的で作り出す手口や、既にある有名コインの名前を悪用して信頼させる手口などさまざまな騙しの手口が存在します。
詐欺コインに騙されないためには、うますぎる儲け話や「絶対、必ず」という言葉を何があっても信用しないことが重要です。
詐欺被害は犯人特定や逮捕が難しく、被害の回復の可能性がかなり低い犯罪と言われていますので、詐欺被害に遭わないように未然に防ぐことがとても大切です。
この記事を参考にしていただき、少しでも怪しいと思ったらその話には乗らないようにしましょう。

【仮想通貨詐欺被害の疑いがある方へ】
仮想通貨詐欺被害の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士への無料相談が可能。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら
\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。
こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。
当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。
当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。
当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。
本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。