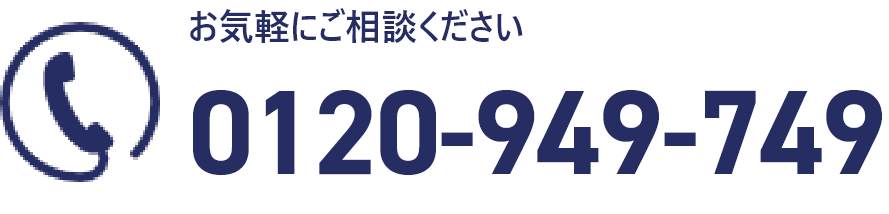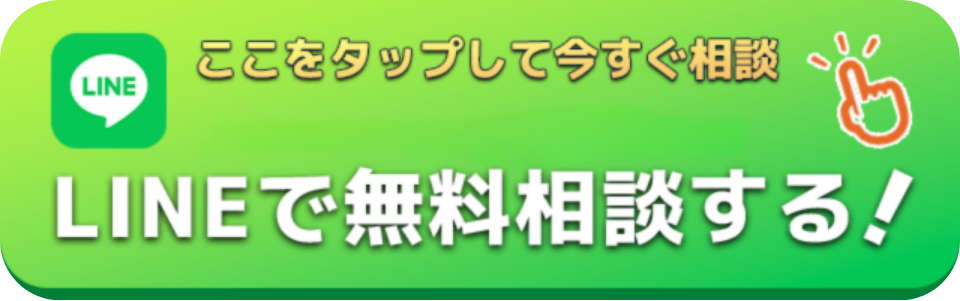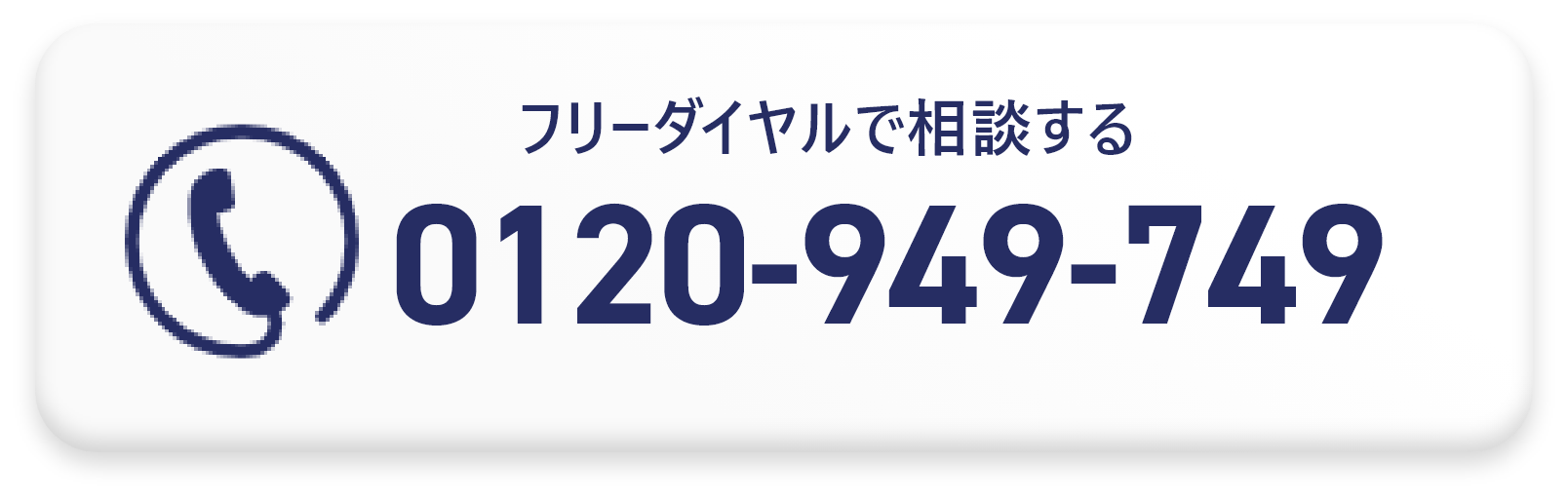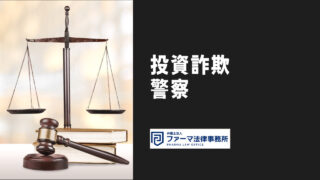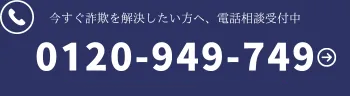副業詐欺の被害に遭い返金を求めるケースが急増しています。
副業で収入を増やしたいという願望を持つ方々を狙った詐欺の手口は巧妙化してきており、被害に気づいた時にはすでに多額のお金を支払ってしまっているケースも少なくありません。
本記事では、副業詐欺の定義から始まり、被害に遭った際の返金方法、専門家への相談のポイントまで徹底解説します。
【副業詐欺被害の疑いがある方へ】
副業詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所には、ネット詐欺に強い弁護士が在籍しています。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺とは?
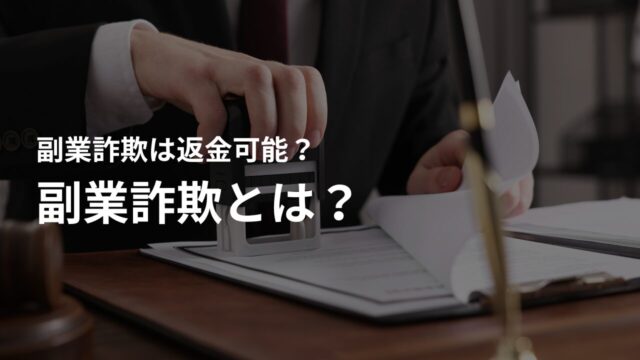
副業で収入を増やしたいと考える方を標的にした「副業詐欺」の被害が年々増加しています。
SNSや動画投稿サイトなどで「スマホ一台で簡単に稼げる」「誰でも簡単に月収〇〇万円」といった魅力的な広告を見かけることがありますが、これらは多くの場合、副業詐欺の入り口となっています。
実際にどのようなものが副業詐欺に該当するのか、その定義や典型的な手口について詳しく見ていきましょう。
副業詐欺の定義
副業詐欺とは、「スマホ一台で簡単に稼げる」などと謳い、実際には稼ぐことができない(再現性がない)副業の情報や商材を高額で販売している詐欺的商法のことです。
詐欺業者は最初に無料または少額の情報提供から始め、徐々に高額なツールやサポートプランの購入を促すケースが典型的です。
被害者がお金を払っても約束された収入は得られず、さらに「より効果的な方法があります」などと追加の費用を要求されることが多いのが特徴です。
多くの場合、副業詐欺は「情報商材詐欺」の一種とされ、実態のない副業情報を販売することで利益を得る仕組みになっています。
実際に弊所で対応した案件では、最初は数千円の教材購入から始まり、最終的に数百万円を支払ってしまったケースもあります。
また、同様に副業を入り口とした詐欺に「タスク詐欺」と呼ばれるものも存在します。
この詐欺種別は、最初は実際に少額の報酬を支払うことで信頼関係を構築し、その後より高額な案件への参加を促します。専用アカウントの開設や初期費用の支払いを要求し、最終的には意図的に失敗するよう設計されたタスクを課して「違約金」や「チーム損失の補填」などの名目で高額な金銭を請求するケースが相次いでいます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。

副業詐欺の典型的な手口
副業詐欺の手口はさまざまであり、一つの手口に限らず「副業を入り口とした詐欺」として警戒する必要があります。
例えば一例として、以下のようなパターンが多く見られます。
まず、SNSや検索広告などで「誰でも簡単に稼げる」と宣伝し、興味を持った方に対して無料または少額の情報商材(電子書籍やPDFなど)を提供します。
この情報商材には具体的な稼ぎ方はほとんど記載されておらず、「さらに詳しい情報が必要」として高額なツールやサポートプランを紹介するという流れです。
被害者が「お金がない」と断っても、「すぐに元が取れる」「返金保証がある」などと説明して購入を促し、時には複数の消費者金融からの借入を勧めるケースもあります。
特に注意すべきは、電話勧誘や遠隔操作アプリを使った強引な契約です。
カードの番号を聞き出して勝手に決済されたり、遠隔操作で金融機関の申込みをさせられるケースもあります。
また、「先着〇〇名限定」「あと3席」などと焦らせる手法や、「〇〇さんも成功した」といった架空の成功例を示す手法も使われます。
このほかにも副業詐欺の手口について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

副業詐欺の違法性についても知っておく
副業詐欺は単に道徳的に問題があるだけでなく、もちろん法的にも様々な問題を含んでいます。
副業詐欺の違法性を理解しておくことで、被害に遭った際の法的対応の可能性が広がります。
法的に義務付けられた表記が存在しない
副業詐欺の販売サイトや広告は、多くの場合、法律で義務付けられた表記が欠けています。
特定商取引法では、通信販売を行う事業者に対して、事業者の氏名や名称、住所、電話番号などの連絡先を明記することを義務付けています。
また、販売価格(送料の表示も含む)、支払い方法・時期、商品の引渡し時期、申込みの撤回や契約解除に関する特約なども明記する必要があります。
これらの表記がない、または不十分な場合は、特定商取引法違反となる可能性が高く、それ自体が違法行為です。
副業詐欺業者は法的な責任追及を避けるため、会社名や住所を頻繁に変更したり、連絡先を明記しないケースが多く見られます。
これらの不備があるサイトや広告は要注意で、そこで紹介されている副業は詐欺の可能性が高いと考えるべきでしょう。
広告の内容に偽りがある
副業詐欺では、「簡単に高収入が得られる」「誰でも稼げる」などの誇大広告が多用されています。
このような表現は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や特定商取引法で禁止されている「優良誤認表示」や「有利誤認表示」に該当する可能性があります。
「業界で一番の実績!」「業界最安値!」などの根拠のない表現も違法な表示となります。
特定商取引法では、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
これらの誇大広告や虚偽表示は、契約の取消しや損害賠償請求を主張する根拠となるため、広告内容はスクリーンショットなどで保存しておくことが重要です。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺の返金請求が可能なケースとは
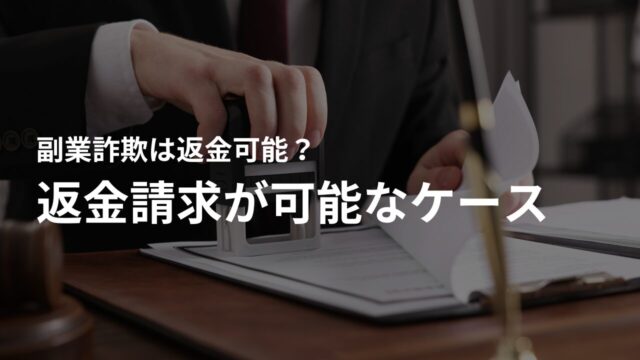
副業詐欺に遭った場合、支払った金銭を取り戻すことは可能なのでしょうか。
ここでは、返金請求が可能なケースと、返金の可能性が低いケースについて解説します。
また、特定のケースではクーリングオフ制度が適用される場合もあるので、その条件も確認しておきましょう。
どのような場合に返金請求できる可能性が高い?
副業詐欺で支払ったお金は、以下のような条件が満たされる場合に返金の可能性が高まります。
詐欺の証拠が十分に存在する
まず、詐欺の証拠を十分に収集できている場合です。
メールやSNSでのやり取り、契約書、振込明細書、広告のスクリーンショットなど、詐欺行為を証明できる証拠があれば、返金請求の根拠となります。
支払い方法によって異なる
次に、支払い方法によって返金の可能性が変わります。
クレジットカード決済の場合は、チャージバック(支払い取消)の申請が可能です。
銀行振込でも、振込先口座の凍結が間に合えば、振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払いを受けられる可能性があります。
クーリングオフの対象になる場合
また、クーリングオフの対象となる取引方法の場合、法定期間内であれば契約解除と全額返金を求められる可能性があります。
8日間
- 訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)- 訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)20日間
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
一方で通信販売には、クーリング・オフ制度がない点には注意が必要です。例えばネット通販で情報商材を購入した場合などは適用されず、特約に従うことになります。
詐欺師の所在が明らかな場合
支払いから間もない場合や、詐欺業者の所在が明確な場合も、返金の可能性は高くなります。
弁護士や司法書士に早期に相談することで、これらの条件を整理し、最適な返金方法を見つけることができるでしょう。
返金の可能性が低いケースとは?
一方で、以下のようなケースでは返金の可能性が低くなる傾向があります。
まず、支払いから長期間(数年)経過している場合です。被害金額が大きく、すぐにでも取り戻したいという方は一刻も早く弁護士等に相談することを推奨します。
- 被害に遭ってから時間が経っている:時間の経過とともに証拠が散逸したり、詐欺業者の所在が不明になったりするケースが多く、返金請求が困難になります。
- 追跡困難な支払い方法:仮想通貨やギフトカードなど、追跡が困難な支払い方法を利用した場合も、返金の可能性は極めて低くなります。
- 詐欺師が海外を拠点にしている:詐欺業者が海外に拠点を置いている場合も、日本の法律に基づく請求が困難になることがあります。
- 証拠が存在しない:契約書や領収書などの基本的な証拠が保存されていない場合も、詐欺の事実を証明することが難しくなります。
ただし、返金の可能性が低いと思われるケースでも、専門家のアドバイスを受けることで思わぬ解決策が見つかることもあります。
あきらめずに弁護士や司法書士、消費者センターなどに相談することをおすすめします。
クーリングオフが適用される副業詐欺
副業詐欺の中には、特定商取引法に基づくクーリングオフが適用される取引形態があります。
前述した通りの期間であれば、クーリングオフが可能となります。
「業務提供誘引販売取引(内職商法)や電話勧誘販売など一定の取引に限定されますが、例えば、「副業を紹介するので」と言って高額なマニュアルやツールを購入させられた場合、契約書面を受け取った日から電話勧誘販売では8日以内、業務提供誘引販売取引では20日以内であれば、クーリングオフが可能です。
また、連鎖販売取引(マルチ商法=サービスを販売する組織に勧誘し、さらに次の販売員を勧誘することで利益を得るビジネスモデル)の場合も、契約書面を受け取った日から20日以内であればクーリングオフが可能です。なお、事業者が法定の契約書面を交付しない場合や、クーリングオフに関する記載がない場合は、期間の制限なくクーリングオフが可能となります。」
ただし、もし解約できないなどと脅されたり、嘘を伝えられた場合は上記のような適用期間が延長される可能性があります。
また、クーリング・オフは書面(はがき可)・電磁的記録で送付するのが一般的です。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺に遭った際にすべきこと – 返金の可能性を高める行動
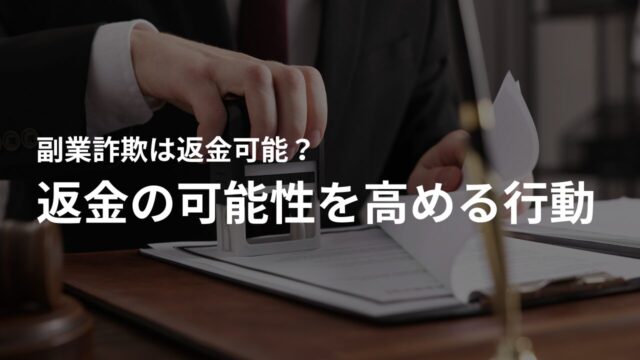
副業詐欺の被害に気づいたら、迅速かつ適切な対応が返金の可能性を高める鍵となります。
被害を最小限に抑え、返金の可能性を最大化するためには、支払いの停止、証拠の確保、業者とのやり取りの記録など、具体的な行動を取ることが重要です。
ここでは、被害に遭った直後にすべき具体的な対応方法について解説します。
「支払いを止める」 – クレジットカード・銀行振込の対応策
副業詐欺に気づいたら、まず最初に行うべきは追加の支払いを止めることです。
クレジットカード決済の場合、直ちにカード会社に連絡し、不正利用または詐欺被害の疑いがあることを伝え、該当の請求に対する支払い保留(チャージバック)を申請します。
多くのカード会社は、詐欺の疑いがある場合、一時的に支払いを保留し調査を行う制度を設けています。
この際、詐欺の証拠(広告、やり取りの記録など)を提出することが重要です。
銀行振込の場合は、直ちに振込先の金融機関に連絡し、詐欺被害の可能性を伝えて口座凍結を依頼します。
口座凍結は金融機関の判断によりますが、詐欺の可能性が高いと判断されれば実施される可能性があります。
また、自動引き落としが設定されている場合は、その停止手続きも忘れずに行いましょう。
定期的な支払いが予定されている場合は、銀行やカード会社に引き落とし停止の手続きを行うことで、被害の拡大を防ぐことができます。
「証拠を確保する」 – メール・LINE・契約書・振込明細を保存
返金請求の成功率を高めるためには、副業詐欺に関するあらゆる証拠を確保することが不可欠です。
具体的には、広告のスクリーンショット、メールやLINEなどのメッセージのやり取り、契約書、振込明細書、商品説明資料などが重要な証拠となります。
特に重要なのは、「誰でも簡単に稼げる」「必ず利益が出る」といった誇大広告の内容や、業者から送られてきた説明資料です。
これらは消費者契約法や特定商取引法に基づく契約取消しの根拠となります。
デジタルデータは印刷して保存するだけでなく、電子データとしてもバックアップを取っておくことをおすすめします。
SNSやWebサイトの情報は削除される可能性があるため、見つけた時点ですぐにスクリーンショットを取っておきましょう。
また、業者との電話でのやり取りがある場合は、通話内容をメモに残しておくか、可能であれば通話を録音しておくと良いでしょう(通話録音は相手に伝えた上で行うのがベストプラクティスです)。
「業者とのやり取りを記録」 – 詐欺の証拠を集めるポイント
副業詐欺業者とのすべてのやり取りは、返金請求の重要な証拠となるため、詳細に記録しておくことが重要です。
特にこの段階では、詐欺業者に対して強く非難したり、脅したりするのではなく、冷静に対応することがポイントです。
メールやLINEでのやり取りはすべて保存し、日時が明確に分かるようにスクリーンショットを撮っておきましょう。
電話でのやり取りも、日時、通話相手、通話内容をできるだけ詳細にメモしておくことが大切です。
業者に返金を求める場合も、その要求と業者の回答をすべて記録します。
「返金保証がついている」と説明されていた場合は、その部分の広告や説明資料を特に注意して保存しておきましょう。
また、業者の態度が急に変わったり、連絡が取れなくなったりした時点も記録しておくと、詐欺の意図を証明する材料になります。
これらの証拠は、消費者センターや弁護士への相談時、そして法的手続きの際に非常に重要な役割を果たします。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺の返金手続き – ケース別の対応策
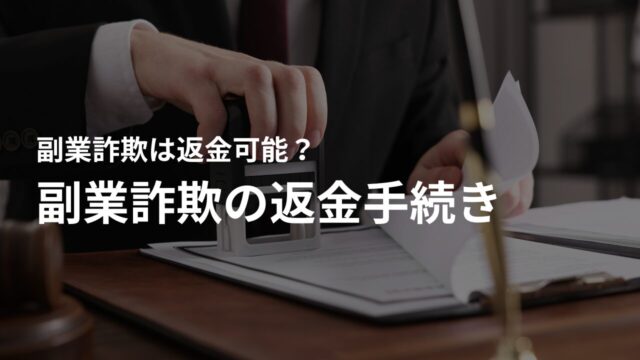
副業詐欺の返金を求める際、支払い方法によって取るべき対応が異なります。
クレジットカード、銀行振込、電子マネー・仮想通貨など、それぞれの支払い方法に応じた効果的な返金手続きについて解説します。
また、消費者契約法や特定商取引法に基づいた契約取消しの可能性についても確認していきましょう。
「クレジットカード払い」の場合 – チャージバック申請の流れ
クレジットカードで支払いを行った場合、チャージバック(支払い取消)制度を利用することが最も効果的な返金方法です。
チャージバックとは、カード会社を通じて支払いを取り消す制度で、商品やサービスが提供されなかった場合や詐欺被害にあった場合に申請できます。
チャージバックの申請手順は以下の通りです。
- まず、カード会社のカスタマーサービスに連絡し、詐欺被害の可能性を伝えます。
- 次に、カード会社の指示に従って必要書類(詐欺の証拠となる資料など)を提出します。
- カード会社が調査を行い、妥当と判断されれば支払いが取り消されます。
チャージバック申請は一般的に支払いから120日以内(カード会社によって異なる)に行う必要があるため、詐欺に気づいたらすぐに行動することが重要です。
割賦販売法に基づく「支払停止の抗弁」も有効で、一定の条件を満たせば支払いを拒否できます。
ただし、一度引き落としが完了している場合は、チャージバックではなく返金請求となり、手続きがやや複雑になります。
「銀行振込」の場合 – 振り込め詐欺救済法を活用する方法
銀行振込で支払いを行った場合は、「振り込め詐欺救済法」を活用することで返金を受けられる可能性があります。
この法律は、詐欺的な目的で開設された口座への振込被害者を救済するためのものです。
振り込め詐欺救済法を活用するための手順は以下の通りです。
- まず、振込先の銀行に詐欺被害の疑いがあることを直ちに連絡します。
- 次に、警察に被害届を提出し、受理番号を取得します。
- 銀行が口座凍結の判断をした場合、公告が行われ、被害届を出した方は被害回復分配金の支払いを受けられる可能性があります。
ただし、この方法は詐欺業者が振込金を引き出す前に口座が凍結されることが条件となります。
被害に気づいたらすぐに行動することが極めて重要です。
また、口座内の残高が被害総額より少ない場合は、一部の返金しか受けられないことにも注意が必要です。
それでも、銀行振込による詐欺被害の場合、まずは振込先銀行への連絡を最優先に行いましょう。
「電子マネー・仮想通貨」の場合 – 返金が難しい理由と対処法
電子マネーや仮想通貨で支払いを行った場合、残念ながら返金を受けることは非常に困難です。
これらの支払い手段は匿名性が高く、一度送金すると取り戻すことが技術的に難しいためです。
電子マネーや仮想通貨での支払いの場合、以下の対応が考えられます。
- まず、支払いサービス提供会社に連絡し、詐欺被害の可能性を伝えます(ただし、多くの場合、サービス提供会社が介入できる余地は限られています)。
- 次に、警察に被害届を提出します。特殊詐欺対策部門が捜査を行い、詐欺グループが検挙された場合に被害回復の可能性が出てきます。
- 最終的には、民事訴訟などの法的手段を検討しますが、相手の特定が難しい場合が多いです。
電子マネーや仮想通貨による支払いを要求されること自体が詐欺の警告サインであることを認識しておきましょう。
これらの支払い手段は、正規のビジネスでは稀であり、詐欺師が好んで利用する手段です。
今後の被害防止のためにも、見知らぬ相手からの電子マネーや仮想通貨での支払い要求には応じないようにすることが重要です。
「消費者契約法・特定商取引法」に基づく契約取消しの可能性
副業詐欺による契約は、消費者契約法や特定商取引法に基づいて取り消せる可能性があります。
消費者契約法では、事業者が「重要事項について事実と異なることを告げた」場合や「将来の不確実な事項について断定的判断を提供した」場合などに、契約の取消しを請求できます。
例えば、「誰でも簡単に稼げる」「絶対に利益が出る」といった断定的な表現で勧誘された場合、消費者契約法第4条に基づいて契約を取り消すことができる可能性があります。
また、特定商取引法では、クーリングオフ期間を過ぎていても、業務提供誘引販売取引や連鎖販売取引で不実の告知があった場合に契約の取消しを請求できます。
これらの法律に基づく取消しは、専門的な知識を要するため、消費者センターや弁護士に相談することをおすすめします。
契約取消しが認められれば、支払った金銭の返還を求めることができるため、詐欺被害回復の有効な手段となります。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺に関する警察・行政機関への相談方法
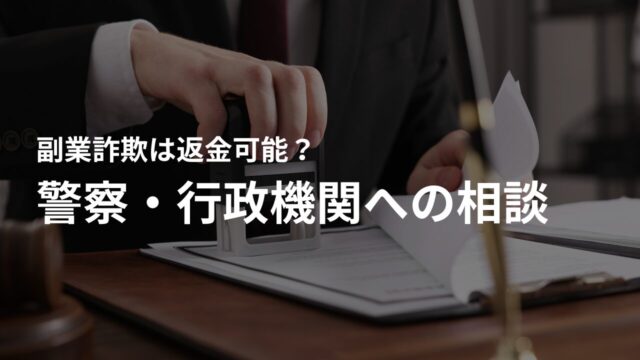
副業詐欺の被害に遭った場合、警察や行政機関への相談も有効な選択肢です。
しかし、どのような証拠を準備すべきか、警察への被害届提出は実際に返金につながるのか、消費者センターへの相談はどのようなメリットがあるのかなど、疑問点も多いでしょう。
ここでは、公的機関への相談方法とそのメリットについて詳しく解説します。
「警察に通報する前に準備すべき証拠」
警察に副業詐欺を通報する際は、詐欺の事実を証明するための証拠を可能な限り収集しておくことが重要です。
具体的には、以下のような証拠を準備しておくと、警察の捜査がスムーズに進む可能性が高まります。
- 業者とのメールやLINEなどのやり取りの記録
- 契約書や利用規約のコピー
- 振込明細書や領収書
- 広告のスクリーンショット
- 業者の会社名や連絡先の情報
また、被害状況を時系列で整理したメモも作成しておくと良いでしょう。
いつ、どのような広告を見て、どのようなやり取りがあり、いくら支払ったのかを明確にしておくことで、警察への説明がしやすくなります。
さらに、同様の被害にあった人の情報があれば、それも併せて提供することで、組織的な詐欺である証拠となり、警察の捜査が進みやすくなります。
準備ができたら、居住地を管轄する警察署の生活安全課や刑事課に相談するのが一般的です。
警察に被害届を出せば返金されるのか?
多くの方が誤解されているのですが、警察に被害届を出しても、直ちに返金されるわけではありません。
警察の役割は犯罪捜査であり、詐欺師の検挙を目指すものですが、民事上の損害賠償や返金は別の手続きが必要です。
警察への被害届提出と返金の関係は以下の通りです。
- 警察が捜査を行い、詐欺師が検挙された場合、刑事裁判で有罪となれば、刑事裁判の中で「被害弁償」が行われる可能性があります。
- また、刑事事件と並行して民事訴訟を起こすことで、詐欺師に損害賠償を求めることができます。
- 刑事事件の証拠が民事訴訟でも利用できる場合があり、有利に働くことがあります。
ただし、刑事事件の捜査・立件には時間がかかりますし、詐欺師が逃亡していたり、資産を隠していたりする場合は、実質的な返金に至らないこともあります。
そのため、警察への被害届提出と並行して、前述した支払い方法別の返金手続きや、弁護士を通じた法的手続きを進めることが重要です。
消費者センターに相談するメリットと対応策
副業詐欺の被害にあった場合、地域の消費者センターに相談することには多くのメリットがあります。
消費者センターは消費者トラブルの専門機関であり、無料で相談に応じてくれます。
特に副業詐欺のような消費者被害については豊富な知見を持っており、適切なアドバイスを受けられる可能性が高いです。
消費者センターに相談する主なメリットとしては、以下が挙げられます。
- 専門的な知識に基づくアドバイスが得られること
- 業者との間に入って交渉してくれる場合があること
- 行政処分につながる可能性があること(同様の被害が多発している場合)
消費者センターに相談する際も、詐欺の証拠をできるだけ多く準備しておくことが重要です。
消費者センターでの相談内容は記録され、同種の詐欺被害の防止や取り締まりのための貴重な情報となります。
なお、消費者ホットライン(188)に電話すれば、最寄りの消費者センターを紹介してもらえます。
ただし、消費者センターも強制力を持つわけではないため、業者が非協力的な場合は限界があることを理解しておく必要があるでしょう。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
弁護士へ相談するメリットとは?副業詐欺の返金請求を成功させるポイント
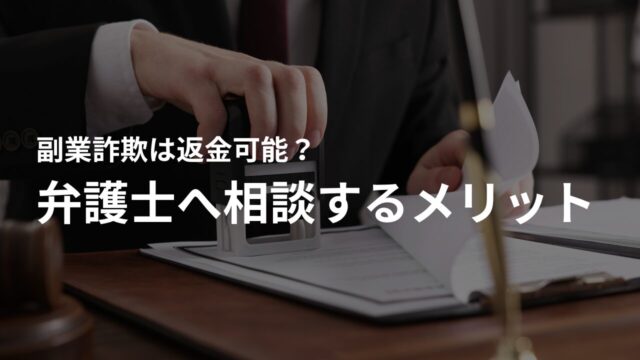
副業詐欺の被害から金銭を取り戻すには、法的な専門知識が必要となるケースが多いです。
弁護士に相談することで、個々の状況に応じた最適な返金方法のアドバイスを受けられます。
示談交渉や訴訟の違い、詐欺業者との直接交渉のリスク、業者の言い逃れパターンなど、弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。
「示談交渉」と「訴訟」の違いとは?
副業詐欺の返金を求める法的手段として、「示談交渉」と「訴訟」の2つの主要なアプローチがあります。
示談交渉とは、裁判外で詐欺業者と交渉し、和解による解決を目指す方法です。
示談交渉のメリットは、裁判よりも短期間で解決できる可能性があること、費用が比較的安く済むこと、非公開で進められることなどです。
一方、デメリットは、相手の誠意に依存するため、非協力的な業者の場合は実効性が低いことです。
訴訟は、裁判所を通じて法的に解決を図る方法です。
訴訟のメリットは、法的強制力があること、判決が出れば強制執行が可能なことなどです。
デメリットは、時間と費用がかかること、相手に資産がなければ実質的な回収が難しいことなどが挙げられます。
どちらの方法が適しているかは個々のケースによって異なるため、弁護士と相談の上で判断することが重要です。
一般的には、まず示談交渉を試み、それが不調に終わった場合に訴訟を検討するという段階的なアプローチが取られることが多いでしょう。
「詐欺業者と直接交渉するリスク
被害者が詐欺業者と直接交渉することには、様々なリスクや問題点が伴います。
まず、詐欺業者は交渉のプロであり、被害者の感情に付け込んだり、巧みな言葉で責任逃れを図ったりする可能性が高いです。
詐欺業者と直接交渉する主なリスクとしては、感情的になって冷静な判断ができなくなる可能性があること、言質を取られて不利な状況に追い込まれる可能性があること、さらなる被害(二次被害)に遭う可能性があることなどが挙げられます。
また、詐欺業者は被害者の脅しや暴言を録音し、後に恐喝罪で逆に訴えるといった手口を使うケースもあります。さらに、「一部返金するから示談書にサインを」と言って、実際には全面的に責任逃れする内容の書面にサインさせるといった手口も存在します。
これらのリスクを避けるためにも、詐欺業者との交渉は弁護士などの専門家に任せるのが賢明です。
弁護士は法的知識と交渉経験を持ち、詐欺業者の言い逃れや誤誘導に惑わされることなく、効果的な交渉を行うことができます。
返金交渉で詐欺業者が使う「言い逃れ」のパターン
副業詐欺業者は返金要求に対して、様々な言い逃れや責任転嫁の手法を用いることが一般的です。
これらのパターンを知っておくことで、交渉時に冷静に対応できるようになります。
詐欺業者がよく使う言い逃れパターンとしては、「契約書にサインしたのはあなた自身」「返金保証の条件を満たしていない」「マニュアル通りに実践していない」「あなただけうまくいかないのは努力不足」などがあります。
また、「担当者が変わった」「会社の方針が変わった」と言って責任の所在をあいまいにしたり、「今は資金繰りが厳しいから待ってほしい」と時間稼ぎをしたりするケースも多いです。
さらに悪質なケースでは、「返金するから追加で〇〇万円支払ってほしい」と言って、さらなる被害を生み出そうとするパターンもあります。
このような言い逃れに対しては、冷静かつ毅然とした態度で、具体的な証拠に基づいて主張することが重要です。
しかし、詐欺業者との交渉は精神的負担が大きく、専門知識も必要となるため、やはり弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで返金の可能性が上がる!
副業詐欺の返金を求める場合、弁護士に依頼することで成功率が大幅に向上する可能性があります。
弁護士は法律の専門家であり、詐欺被害の回復に関する知識と経験を持っています。
弁護士に依頼するメリットとしては、法的知識に基づいた適切な返金方法を提案してもらえること、詐欺業者に対する心理的プレッシャーとなること、交渉や訴訟の負担から解放されること、二次被害のリスクを軽減できることなどが挙げられます。
特に、弁護士名での内容証明郵便は、詐欺業者に対して強いインパクトを与えることができます。
「弁護士が介入した」という事実だけで、詐欺業者が返金に応じるケースも少なくありません。
また、弁護士は消費者契約法や特定商取引法など、関連法規の適用可能性を専門的に検討し、最適な法的戦略を立てることができます。
弁護士費用が心配される方もいるかもしれませんが、多くの弁護士事務所では初回相談無料のサービスを提供しています。
まずは相談してみて、費用対効果を含めた総合的な判断をするのがおすすめです。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺の返金に関するよくある質問
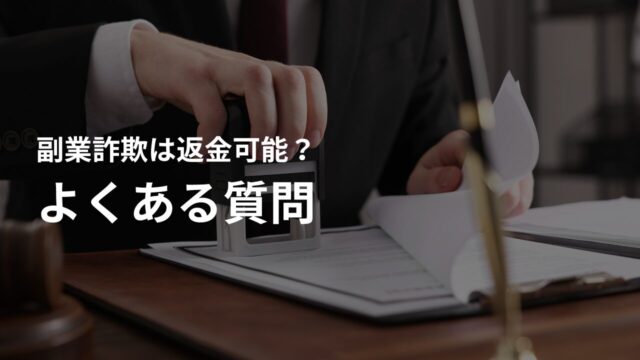
副業詐欺の被害に遭った方からは、返金の可能性や手続きについて様々な疑問が寄せられます。
ここでは、契約書がない場合の対応、業者が連絡を無視するケース、家族や友人が被害に遭った場合のサポート方法、弁護士費用の目安、業者が逃げてしまった場合の対応など、よくある質問について回答します。
「契約書がなくても返金請求できる?」
副業詐欺被害において、正式な契約書がなくても返金請求は可能です。
契約は必ずしも書面でなく、口頭や電子的なやり取りでも成立するためです。
契約書がない場合でも、メールやLINEなどのメッセージ、振込明細書、商品説明の資料、広告のスクリーンショットなど、取引の証拠となるものを集めることが重要です。
これらの証拠から契約の存在と内容を証明することができます。
また、クレジットカード決済の場合は、利用明細が重要な証拠となります。
銀行振込の場合も、振込明細書は取引の証拠として有効です。
さらに、詐欺業者とのやり取りを記録していれば、それも有力な証拠となります。
ただし、契約書がない場合は証拠集めがより重要になるため、できる限り多くの関連資料を収集し、取引の経緯を時系列で整理しておくことをおすすめします。
不安な場合は、弁護士や消費者センターに相談し、具体的な証拠の有効性を確認してもらうとよいでしょう。
「副業詐欺業者が連絡を無視している場合の対処法は?」
副業詐欺業者が連絡を無視する場合、法的手段を視野に入れた段階的なアプローチが効果的です。
まず考えられるのは、内容証明郵便での返金要求です。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を相手に送ったかを法的に証明できる郵便サービスです。
返金要求の意思を明確に伝え、期限を設けて回答を求めることで、業者に対して法的な圧力をかけることができます。
それでも反応がない場合は、弁護士に依頼して法的手続きを進めることを検討します。
弁護士名での内容証明郵便は、より強い効果が期待できます。
また、消費者センターや国民生活センターに相談することも有効です。
同様の被害が多発している場合、行政指導や業務停止命令などの行政処分につながる可能性があります。
最終的には、少額訴訟や通常訴訟といった司法手続きを利用することも選択肢となります。
ただし、業者が「夜逃げ」同然に所在不明になっている場合は、返金を受けることが難しくなるのも事実です。
そのような場合でも、警察への被害届提出は行っておくべきでしょう。
「家族や友人が副業詐欺に遭った場合、どうサポートすべき?」
家族や友人が副業詐欺の被害に遭った場合、精神的なサポートと具体的な行動支援の両面からのアプローチが重要です。
まず、責め立てたり批判したりするのではなく、共感的な姿勢で話を聞くことが大切です。
被害者は自責の念や恥ずかしさを感じていることが多いため、「誰でも騙される可能性はある」と伝え、前向きに解決策を一緒に考えていく姿勢が重要です。
具体的な行動支援としては、証拠の収集・整理を手伝ったり、消費者センターや弁護士事務所への相談に同行したりすることが有効です。
また、専門家への相談を勧める際も、「あなたを責めているのではなく、専門家の力を借りて解決するために必要なステップだ」と伝えることが大切です。
さらに、詐欺業者からの追加の連絡があった場合の対応方法をアドバイスするなど、二次被害を防ぐための情報提供も重要です。
被害者が高齢者や判断能力に不安のある方の場合は、法定後見制度の利用や地域の高齢者見守りサービスの活用も検討しましょう。
「返金を弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかる?」
副業詐欺の返金請求を弁護士に依頼する場合の費用は、被害金額や依頼する弁護士事務所によって異なりますが、一般的な費用の目安を解説します。
多くの弁護士事務所では、初回相談料(30分〜1時間程度)は無料か数千円程度で設定されています。
本格的に依頼する場合、一般的には着手金と成功報酬の組み合わせとなります。
例えば「着手金10万円〜30万円・成功報酬返金額の10%〜20%」など、弁護士事務所によって料金設定はさまざまです。
少額の被害(数万円程度)の場合、費用対効果の面から弁護士依頼は現実的でないこともあります。
その場合は、消費者センターへの相談や自分での内容証明郵便の送付などを検討しましょう。
多くの弁護士事務所では分割払いや、被害金額が少額の場合の定額制の料金設定を設けていることもあります。
また、弁護士費用特約付きの保険に加入している場合は、保険を利用できる可能性もあるため、確認してみることをおすすめします。
費用面で不安がある場合は、複数の弁護士事務所に相談し、費用体系を比較検討することも一つの方法です。
「すでに詐欺業者が逃げてしまった場合、返金の可能性は?」
詐欺業者が所在不明になった場合、返金を受けることは困難になりますが、諦める前に検討すべき選択肢があります。
まず、支払い方法によって取るべき行動は異なります。
クレジットカード払いの場合は、カード会社にチャージバックを申請することができます。
支払いから一定期間(多くは120日)以内であれば、審査の上で返金される可能性があります。
銀行振込の場合も、振込先の銀行に詐欺被害の旨を伝え、口座凍結を依頼することで、未引き出し分の資金が戻る可能性があります。
警察への被害届提出も重要で、詐欺グループが後日検挙された場合に、被害回復の可能性が生まれます。
また、弁護士に相談すれば、会社名や代表者名から資産の所在を調査し、強制執行の可能性を探ることもできます。
完全に所在不明となった場合の返金は難しいのが現実ですが、諦める前に専門家に相談することをおすすめします。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
まとめ
副業詐欺の被害に遭った場合、返金を受けるためには迅速かつ適切な対応が不可欠です。
本記事では、副業詐欺の定義から始まり、返金請求の可能性、具体的な手続き方法、専門家への相談ポイントまで詳しく解説しました。
返金の可能性を高めるためには、詐欺の証拠を十分に収集し、支払い方法に応じた適切な対応を取ることが重要です。
クレジットカード払いならチャージバック、銀行振込なら振り込め詐欺救済法の活用、契約内容によってはクーリングオフや契約取消しなど、状況に応じた方法を選択しましょう。
また、警察や消費者センターへの相談も並行して行い、詐欺の事実を公的に記録しておくことも大切です。
特に複雑なケースや高額な被害の場合は、弁護士など専門家への相談が返金成功率を高める鍵となります。
【副業詐欺被害の疑いがある方へ】
副業詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所には、ネット詐欺に強い弁護士が在籍しています。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。
当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。
当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。
当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。
本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。