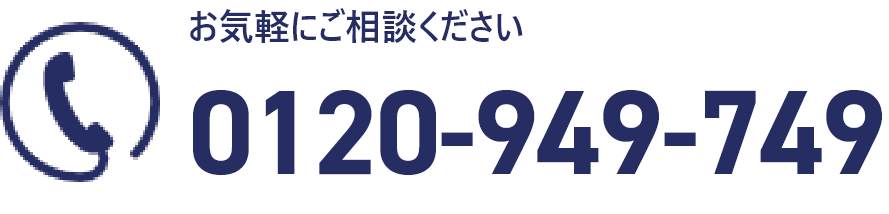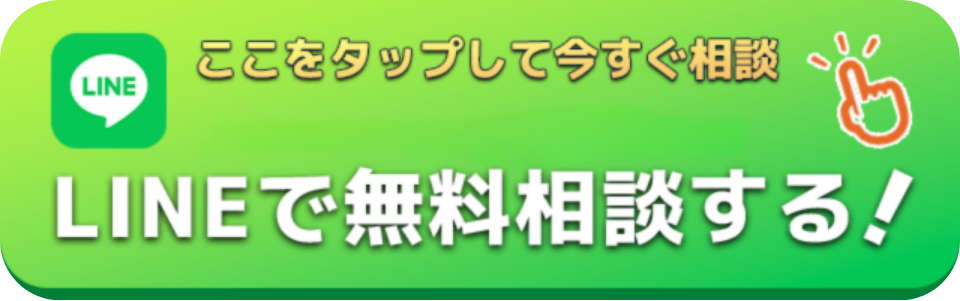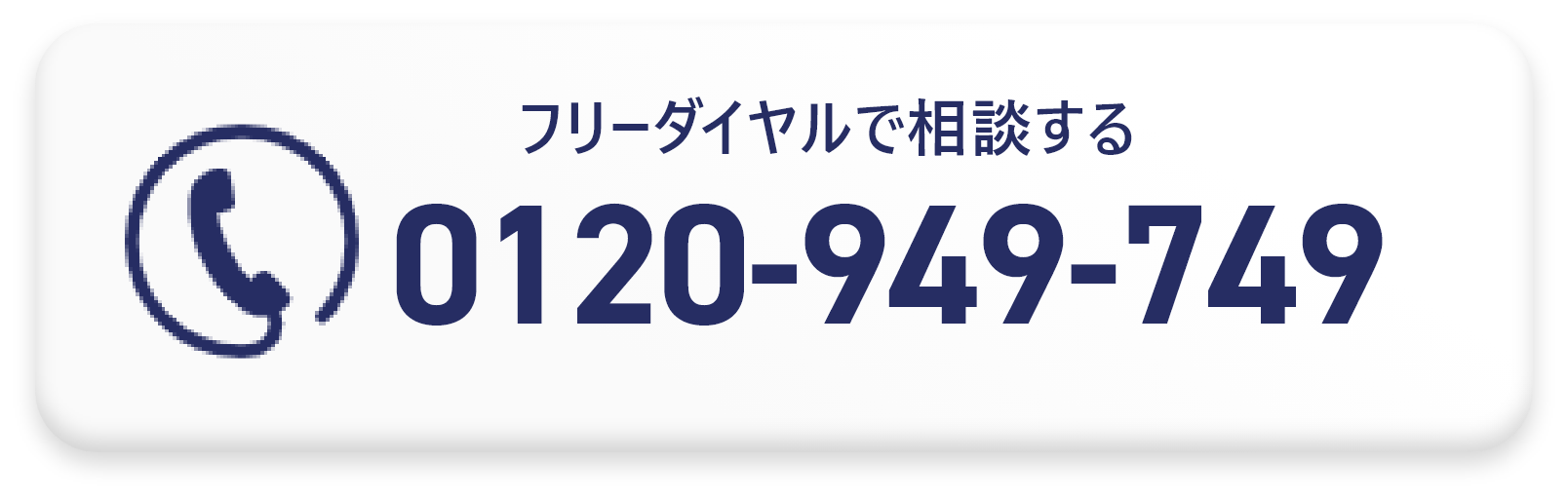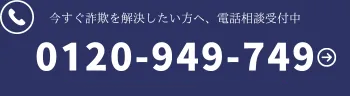副業詐欺の被害は年々増加しており、手口も巧妙化しています。
特にSNSやインターネット広告を活用した新たな手口が次々と現れており、誰もが被害に遭うリスクが高まっています。
本記事では、副業詐欺の具体的な手口と見分け方、そして被害に遭った場合の対処法について詳しく解説します。
【副業詐欺被害の疑いがある方へ】
副業詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所には、ネット詐欺に強い弁護士が在籍しています。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺とは?なぜこんなにも増えているのか
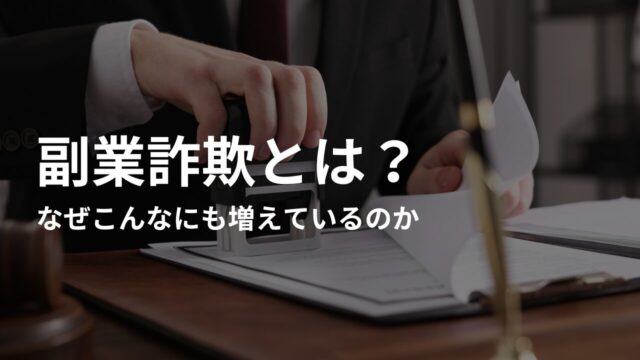
「簡単に稼げる」「必ず儲かる」といった甘い言葉で勧誘し、情報商材の購入や登録料の支払いを要求する詐欺行為が横行しています。
働き方改革に伴い副業への関心が高まる中、その需要に付け込んだ詐欺被害が社会問題となっています。
まずは副業詐欺の実態について見ていきましょう。
そもそも副業詐欺とは?
副業詐欺は、「スマホ1台だけで簡単に収入が得られる」「誰でも月収100万円達成可能」といった魅力的なフレーズで人々を引き寄せる悪質な詐欺です。
詐欺師は最初に登録料の支払いを求めたり、高額な情報商材を購入させたり、「成功のための特別サポートプラン」などの名目で追加契約を迫ったりして、段階的に金銭を搾取していきます。
実際には、宣伝文句とは裏腹に約束された収入を得られることはほとんどなく、支払った金額はすべて損失となってしまいます。このような詐欺の被害に気づいたら、すぐに取引を中止し、証拠を集めて専門機関に相談することが重要です。
早期発見と適切な対応が、被害を最小限に抑える鍵となります。
副業詐欺の最新の被害状況
近年、副業詐欺の被害報告の増加が深刻化しています。
特にSNSを介した投資詐欺や情報商材詐欺による被害が顕著に増加しています。
国民生活センターの発表によると、20代から30代の若年層を中心に被害が拡大しており、以下のような呼びかけも行っています。
被害の特徴として、一度被害に遭った人が再び別の詐欺に遭うケースも多く報告されています。
スマートフォンの普及により、24時間いつでも勧誘メッセージを送れる環境が整ったことも、被害増加の要因となっています。
副業詐欺はなぜ増加しているのか
副業詐欺が増加している背景には、以下のような社会的要因があります。
物価高騰により副収入を求める人が増加する中、SNSの普及により詐欺の手口が巧妙化しています。
AIを活用した自然な文章生成により、詐欺サイトの信頼性が向上している点も特徴です。
コロナ禍以降のオンラインコミュニケーションの一般化により、対面での本人確認が不要な取引が増加したことも要因の一つです。
また、暗号資産やFX取引など、新しい金融商品への関心の高まりに便乗した投資詐欺も増加しています。
個人情報の流出にも要注意
副業詐欺は金銭的な被害だけでなく、個人情報の流出という重大なリスクも伴います。
詐欺師に個人情報を渡してしまうと、その情報が犯罪者間で共有され、「カモリスト」として新たな詐欺の標的にされる危険性があります。
一度流出した個人情報は、複数の詐欺グループで共有され、さまざまな手口で繰り返し狙われる可能性があります。
特に、氏名、住所、電話番号に加え、家族構成や年収などの詳細な個人情報を詐取される場合もあります。
このような情報は、より巧妙な詐欺や別の犯罪に利用される可能性があるため、安易に提供してはいけません。
手口や連絡方法が変化しても、同じ人物が狙われ続けるという特徴があります。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺の主な8つの手口と特徴
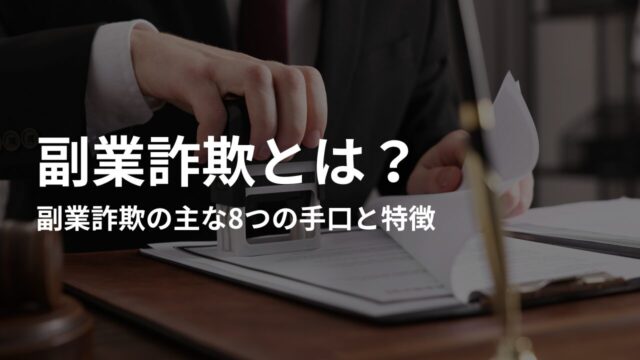
副業詐欺の手口は年々巧妙化し、その種類も多様化しています。
特にインターネットを介した新たな手口が次々と登場し、見分けることが困難になっています。
以下では、代表的な8つの手口と、その特徴について詳しく解説します。
情報商材詐欺|副業詐欺の主な手口①
情報商材詐欺は、副業詐欺の中でも最も多い手口の一つです。
その多くが「高収入を得られる」と謳う情報商材を入り口としています。
安い電子書籍を購入させて、電話勧誘により高額なサポートやコンサルティングを契約をさせる詐欺手法です。
インターネット上で簡単に販売できるため、詐欺グループにとって実行しやすい手口となっています。
https://phamalaw.com/media/zyouhosyozai-henkin/
タスク詐欺|副業詐欺の主な手口②
SNSやインターネット広告を通じて「簡単に稼げる」と謳うタスク詐欺が急増しています。
最初は少額の報酬を実際に支払うことで信頼を得た後、高額な手数料を要求するのが特徴です。
スマートフォンでの簡単な作業で稼げると謳い、「高額なタスクをするために振込みが必要」「出金するには手数料が必要(実際には手数料を振り込んでも出金できない)」などと理由をつけて請求する手口が一般的です。
実際の作業は存在せず、報酬を受け取るための手数料名目で次々と金銭を要求されます。
特に若年層をターゲットにしており、少額から始められる点を強調して勧誘を行います。

出会い系のサクラ勧誘|副業詐欺の主な手口③
主に女性をターゲットにした出会い系サイトのサクラ勧誘も深刻な問題となっています。
「メールの返信だけで高収入」と謳い、登録料や利用料を騙し取る手法です。
実際の仕事内容は存在せず、システム利用料や登録料など、様々な名目で金銭を要求されます。
「会員とメール交換するだけで月収30万円」など、非現実的な収入額を提示して勧誘を行います。
報酬を受け取る段階になると、さらに手数料が必要だと言われ、支払いを続けさせられます。
副業斡旋・資格取得サポート詐欺|副業詐欺の主な手口④
副業の紹介や資格取得支援を謳って金銭を騙し取る手口です。
「確実に仕事を紹介する」と約束しながら、高額な登録料や教材費を請求する手法が特徴です。
実際の副業紹介や資格取得支援は行われず、支払いだけが発生する仕組みになっています。
資格取得のサポートと称して、市販の参考書程度の内容しかない教材を高額で販売するケースも多く見られます。
支払い後は連絡が取れなくなったり、さらなる追加料金を要求されたりするパターンが一般的です。
メールレディー詐欺|副業詐欺の主な手口⑤
女性をターゲットにした「メールレディー」という名目の詐欺が増加しています。
「相談に乗るだけで高収入」と謳い、登録料や研修費用を騙し取る手口です。
高所得者の異性とメールでやり取りするという設定で、最初から実在しない仕事を提示します。
登録後は、研修費用やシステム利用料など、様々な名目で支払いを要求されます。
実際の報酬は一切支払われず、支払った金額の返金も期待できません。
輸入品の販売ビジネス|副業詐欺の主な手口⑥
輸入ビジネスを装った詐欺も横行しています。
「海外商品の仕入れルートを提供する」と称して、高額な顧問料やコンサル料を請求する手口です。
実際の輸入ビジネスには、通関手続きや為替リスクなど専門的な知識が必要であり、素人には難しい分野です。
しかし詐欺グループは「誰でも簡単にできる」と謳い、高額な契約を結ばせます。
支払い後は具体的なサポートは一切ありません。
投資をレクチャーする|副業詐欺の主な手口⑦
投資のノウハウを提供すると称して、情報商材やツールを販売する詐欺です。
「毎月確実に利益が出る投資手法」と謳い、高額な投資システムを販売する手口です。
実際には利益の出ない投資手法や、出金できない仕組みの自動売買ツールが提供されます。
https://phamalaw.com/media/fx-automatic-trading-fraud/
最初は少額の情報商材から始まり、徐々に高額なシステムの購入を促されます。
投資の専門用語を多用して信頼性を演出し、素人を騙す手口が特徴です。
ネットショップ運営代行詐欺|副業詐欺の主な手口⑧
ECサイトの運営代行を装った詐欺が急増しています。
「商品の仕入れから発送まですべて代行する」と謳い、高額な初期費用を騙し取る手法です。
サイト構築費用や在庫確保の名目で、数十万円規模の支払いを要求されることが一般的です。
支払い後は、売上が全く上がらない、もしくは運営者と連絡が取れなくなるケースがほとんどです。
実際の商品販売や運営支援は一切行われず、初期費用の支払いだけで終わってしまいます。

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺を見破るための重要チェックポイント
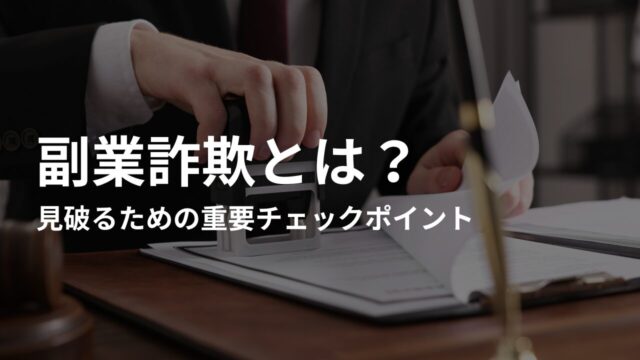
副業詐欺は巧妙化していますが、いくつかの共通する特徴があります。
これらのチェックポイントを意識することで、多くの詐欺被害を未然に防ぐことができます。
以下では、詐欺を見破るための7つの重要なポイントを解説します。
事前にお金を払う必要がある
正当な副業であれば、働いてから報酬を受け取るのが一般的です。
仕事を始める前に登録料や入会金、教材費などの支払いを求められる場合は、副業詐欺の可能性があるため要注意です。
特に「すぐに元が取れる」「払った以上の収入が確実に得られる」といった説明がある場合は、詐欺の可能性が極めて高いでしょう。
正当なビジネスであれば、事前の支払いを強要することはありません。
初期費用の支払いを急かされたり、期間限定の特別価格を強調されたりする場合は、詐欺を疑う必要があります。
コミュニティへの参加を勧められる
成功者が集まるコミュニティや会員制のグループへの参加を強く勧められる場合は、副業詐欺の可能性があるため注意が必要です。
LINE等のSNSグループに招待され、すでに稼いでいる会員の声を見せられる手法が一般的です。
実際には架空の成功者を演じる詐欺グループのメンバーが、新規参入者を安心させる役割を担っています。
コミュニティ参加費用として高額な支払いを要求されることも多く、一度参加すると退会を認めないケースもあります。
グループ内での情報共有を装って、さらなる詐欺的商材の購入を促されることも特徴です。
稼ぐ方法があまりにも簡単すぎる
「スマホだけで簡単に稼げる」「1日30分の作業で月収100万円」など、非現実的な収入を謳う副業には要注意です。これらの文言は副業詐欺にありがちな特徴です。
誰でも簡単に大金が稼げるような仕事は、実際には存在しません。
正当な副業であれば、必要なスキルや経験、リスクについても明確に説明があるはずです。
収入を得るために必要な時間や労力について、具体的な説明がない案件は避けるべきです。
特に「寝ていても稼げる」「放置で収入が得られる」といった表現には強い警戒が必要です。
仕事内容が詳しく記載されていない
具体的な仕事の内容や収入を得るまでのプロセスが明確に説明されていない案件は危険です。副業詐欺である可能性があります。
「簡単な作業」「誰でもできる仕事」など、抽象的な表現で具体的な説明を避ける傾向があります。
正当な求人であれば、業務内容や必要なスキル、勤務条件などが詳細に記載されているはずです。
実際の業務内容を確認しようとしても、「登録後に説明する」「料金を支払ってから開示する」といった対応は詐欺の典型的な特徴です。
事前に仕事内容を確認できない案件には、絶対に応募すべきではありません。
広告で「絶対に稼げる」など過剰な表現を使っている
「必ず儲かる」「絶対に成功できる」といった断定的な表現を使用する広告には注意が必要です。副業詐欺である可能性があります。
「確実」「絶対」「必ず」などの言葉を多用し、リスクについての説明が一切ないのが特徴です。
ビジネスには必ずリスクが伴います。リスクについて一切触れない案件は、詐欺の可能性が高いと考えられます。
誇大広告は違法であり、正当な事業者であれば使用しない表現です。
過度に期待を煽るような表現を見かけたら、それだけで詐欺を疑うべきでしょう。
SNS等で成功例をアピールしている
SNSで豪華な生活ぶりや高額な収入を誇示する投稿には要注意。こちらも副業詐欺にありがちな特徴に当てはまります。
高級車や高級時計、札束の写真など、見せかけの成功例を使って信用を得ようとする手口が増えています。
実際にはレンタルやフェイク画像を使用していることが多く、成功者を装って被害者を勧誘します。
特にインスタグラムやXなどのSNSでは、架空の成功体験を投稿する詐欺グループが横行しています。
写真や動画による派手な成功アピールは、むしろ詐欺を疑うべき重要なサインです。
運営会社の情報が十分に記載されていない
正当な企業であれば、会社の基本情報を明確に開示しているはずです。
会社名、所在地、代表者名、問い合わせ先などが不明確な場合は、副業詐欺の可能性が極めて高いといえます。
特に法人登記や事業許可の有無、過去の事業実績などを確認できないケースは要注意です。
メールアドレスや携帯電話番号のみの連絡先しか記載がない場合も危険信号です。
実際のオフィスが存在しない、バーチャルオフィスだけの企業にも警戒が必要です。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
もし副業詐欺に遭ってしまったらどうすべき?
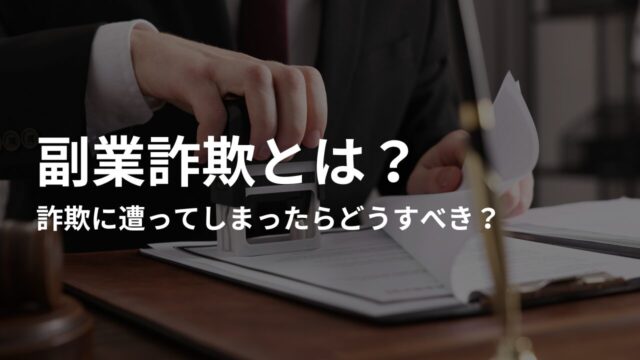
副業詐欺の被害に遭った場合、迅速な対応が被害の拡大防止と回復につながります。
発覚後すぐの対応が、被害回復の重要な分かれ道となります。
以下では、具体的な対処方法と相談先について解説します。
副業詐欺でクーリングオフは可能?
副業詐欺の被害に遭った場合、クーリングオフ制度を利用できる可能性があります。
契約形態や取引方法によって、返金を求められる場合があります。
まずはクーリングオフ制度の概要を確認しましょう。
クーリングオフとは何か
クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
消費者を守るための制度であり、事業者の同意なく一方的に契約を解除できます。
クーリングオフは契約書面を受け取った日から起算され、取引形態によって期間が異なります(契約書面に不備があった場合はそれ以降でも可能)。
訪問販売や電話勧誘販売の場合は契約書面を受け取ってから8日間となっています。
解約に伴う損害賠償や違約金も請求されることはありません。
https://phamalaw.com/media/cooling-off-period/
どんな副業詐欺がクーリングオフの対象になる?
副業詐欺の中でも、特定商取引法で定められた取引形態(特定継続的役務提供、連鎖販売取引、訪問販売、 業務提供誘引販売取引)に該当するものがクーリングオフの対象となります。
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
通信販売で購入した情報商材などは、原則としてクーリングオフの対象外です。ただし、例外的にクーリングオフや返品が認められるケースもありますので、疑問がある場合は消費生活センターや法律事務所に確認してください。
クレジットカードの引き落とし停止
副業詐欺に遭ってしまって、もしクレジットカードで支払いを行った場合、早急に引き落としの停止手続きを取る必要があります。
カード会社に連絡し、不正・詐欺被害である旨を申し出ることで、支払いを止められる可能性があります。
カード会社への連絡は24時間体制で受け付けているため、被害に気付いたらすぐに連絡することが重要です。
また、今後の不正利用を防ぐため、カードの再発行を依頼することも検討すべきです。
セキュリティコードまで詐欺師に伝えてしまった場合は、カードの利用停止措置が必要です。
クレジットカードの場合はチャージバックシステムによる返金の可能性も
クレジットカード決済の場合、チャージバックという制度を利用できる可能性があります。
商品やサービスが提供されないなど、契約内容が履行されない場合に、支払いを取り消せる制度です。
ただし、申請期限や条件が厳格に定められているため、早期の対応が必要不可欠です。カード会社によって審査基準が異なり、返金されるかどうかはケースバイケースとなります。
国際ブランドのカードの場合、120日以内の申請が必要となることが一般的です。
証拠となる契約書やメールのやり取りなどを保管しておくことが重要です。
副業詐欺に遭った場合の相談先
被害に遭った場合、複数の専門機関に相談することで、より効果的な解決が期待できます。
それぞれの機関が持つ専門性を活かした対応が可能です。
以下に、主な相談先とその特徴を解説します。
国民生活センター|副業詐欺被害の相談先①
国民生活センターは、消費者トラブル全般の相談窓口として機能しています。
全国の消費生活相談情報を集約し、同様の被害防止に向けた情報提供も行っています。
専門の相談員が対応し、問題解決に向けた具体的なアドバイスを提供してくれます。
相談は無料で行え、必要に応じて法律の専門家や他の機関も紹介してくれます。
特に新手の詐欺に関する情報も豊富で、最新の被害傾向も把握できます。
消費生活センター|副業詐欺被害の相談先②
各地域の消費生活センターでは、より身近な相談窓口として機能しています。
地域の実情に詳しい相談員が、具体的な解決策を提案してくれます。
必要に応じて事業者との交渉を支援してくれる場合もあります。
相談内容は全国のデータベースで共有され、被害の拡大防止にも役立てられます。
直接訪問しての相談も可能で、書類の確認なども行えます。
消費生活相談窓口|副業詐欺被害の相談先③
全国の市区町村に設置されている消費生活相談窓口も、重要な相談先の一つです。
地域に密着した相談窓口として、きめ細かな対応が期待できます。
消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの相談窓口に接続されます。
土日祝日も対応している窓口もあり、気軽に相談できる環境が整っています。
相談は無料で、個人情報も厳重に管理されます。
警察|副業詐欺被害の相談先④
被害額が高額な場合や、明確な詐欺の証拠がある場合は、警察への被害届の提出を検討します。
警察では、詐欺事件として立件できるか慎重に判断し、捜査を行います。
被害届の提出時には、できるだけ詳細な証拠を用意することが重要です。
メールやSNSでのやり取り、振込記録など、できるだけ多くの証拠を保全しておきましょう。
同様の被害報告が多数ある場合、より本格的な捜査につながる可能性があります。
https://phamalaw.com/media/fraud-victim-police/
弁護士|副業詐欺被害の相談先⑤
法的な対応が必要な場合は、弁護士への相談が効果的です。
返金請求や損害賠償請求など、法的手段を用いた解決を図ることができます。
初回相談を無料で行っている事務所も多く、気軽に専門家の意見を聞くことができます。
集団訴訟の可能性がある場合は、より効果的な解決が期待できます。
示談交渉や訴訟提起など、状況に応じた適切な法的対応を提案してくれます。
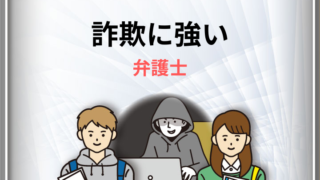
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
副業詐欺に関するよくある質問
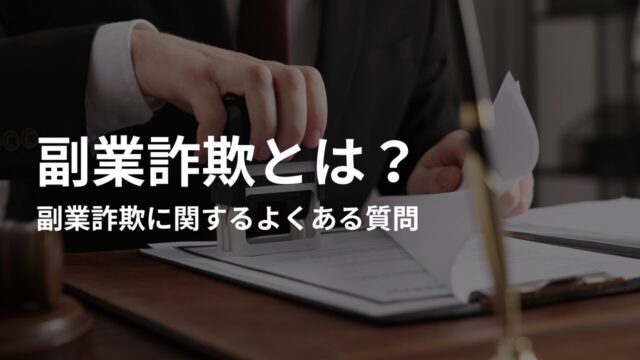
副業詐欺に関して、多くの方から寄せられる疑問や質問についてお答えします。
被害の予防から対処方法まで、実践的な観点から解説します。
以下のQ&Aを参考に、適切な対応を検討してください。
SNSで「簡単に稼げる副業がある」と紹介されましたが、詐欺を見分けるポイントはありますか?
SNSでの副業勧誘には、特に注意が必要です。
「誰でも簡単に稼げる」「初期費用のみで確実に収入が得られる」といった誇大な表現には要注意です。
正当な副業であれば、必要なスキルやリスクについても明確に説明があるはずです。
また、LINEやメッセージアプリでの個別のやり取りを求められる場合も危険信号です。
特に急かされたり、秘密を強要されたりする場合は、詐欺の可能性が極めて高いと考えられます。
情報商材を購入してしまいましたが、返金してもらうことは可能ですか?
情報商材等の通信販売については、クーリングオフ制度がありません。
しかし、広告等に返品について記述がないような場合は、商品を受け取ってから8日間は契約を解除できる可能性があります。
通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
引用元:通信販売|特定商取引法ガイド
契約書や領収書、メールのやり取りなど、証拠となる資料は必ず保管しておきましょう。
クレジットカードで支払ってしまった場合、支払いを止めることはできますか?
クレジットカードでの支払いは、早急な対応で停止できる可能性があります。
カード会社に詐欺被害の旨を申し出ることで、支払い停止の手続きを取ることができます。
チャージバックという制度を利用して、支払いの取り消しを請求できる可能性があります。
ただし、申請には期限があるため、被害に気付いたら即座にカード会社への連絡が必要です。
取引の証拠となる資料を用意し、詐欺被害であることを具体的に説明できるようにしましょう。
副業詐欺の被害に遭った場合、どこに相談すればよいですか?
複数の相談窓口を適切に活用することで、より効果的な解決が期待できます。
消費者ホットライン(188)や警察、弁護士など、状況に応じた相談先を選択することが重要です。
特に初期段階では、消費生活センターに相談することで、適切な対応方法のアドバイスを得られます。
被害額が高額な場合は、弁護士への相談も検討すべきです。
早期の相談が被害の拡大防止と回復につながるため、迷わず専門家に相談することをおすすめします。
騙し取られたお金を取り戻せる可能性はありますか?また、どのような方法がありますか?
詐欺被害の回復は難しい場合が多いですが、状況によっては返金を受けられる可能性があります。
クーリングオフ制度の利用や法的手続きによる返金請求など、複数の方法を検討できます。
被害の早期発見と迅速な対応が、返金の可能性を高める重要な要素となります。
特に弁護士に依頼することで、法的手段を用いた返金請求が可能になります。
集団訴訟への参加や民事訴訟の提起など、状況に応じた対応を検討することができます。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
まとめ
副業詐欺は年々手口が巧妙化しており、誰もが被害に遭うリスクがあります。
被害を防ぐためには、詐欺の特徴を理解し、怪しい案件には安易に手を出さないことが重要です。特に事前の支払いや、非現実的な収入を謳う案件には要注意です。
万が一被害に遭った場合でも、早期の対応で被害を最小限に抑えることができます。
消費生活センターや弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることが大切です。
被害の予防と対処、両面での意識を持つことで、安全な副業活動を行うことができます。
【副業詐欺被害の疑いがある方へ】
副業詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所には、ネット詐欺に強い弁護士が在籍しています。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。
当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。
当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。
当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。
本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。