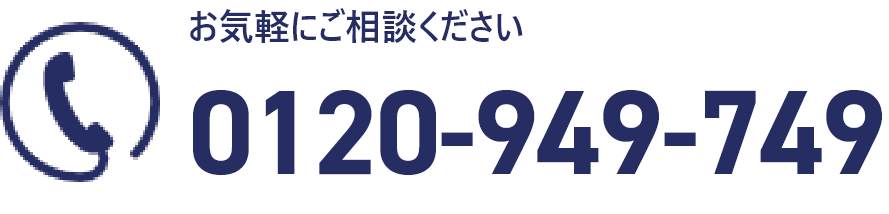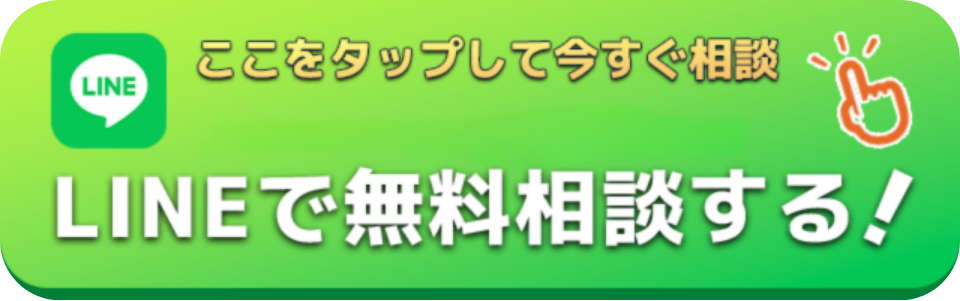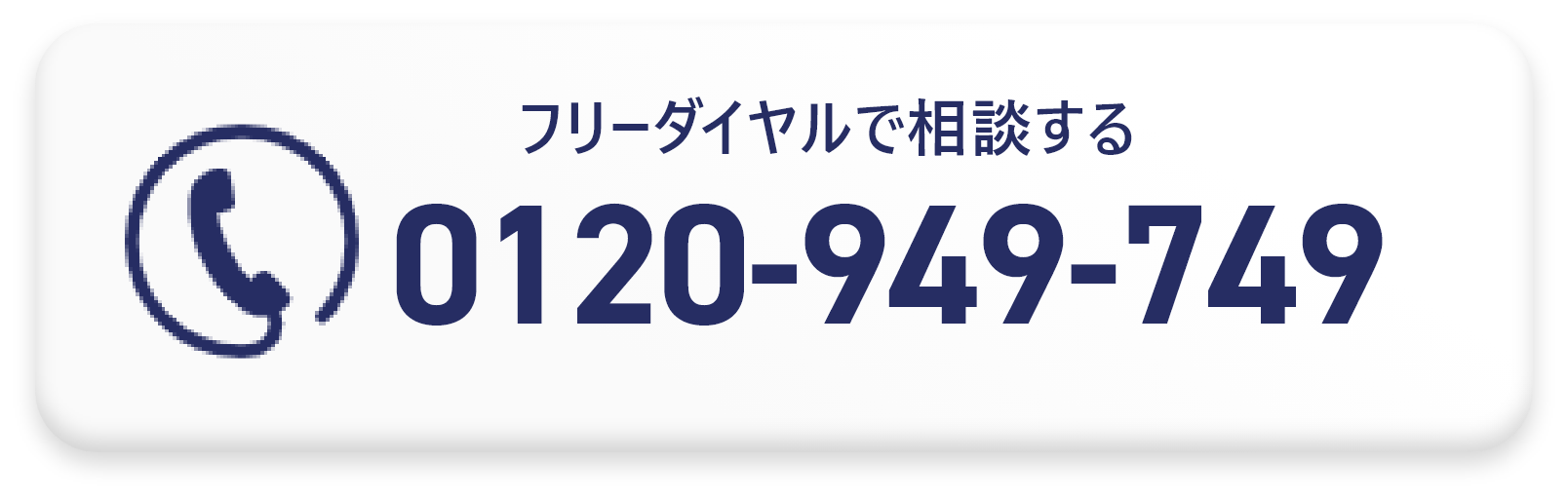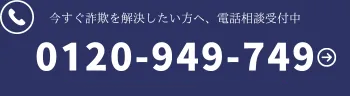仮想通貨詐欺の被害に遭い、「失ったお金は返金できるのか?」と不安になる方は少なくありません。
本記事では、仮想通貨詐欺の代表的な手口とその特徴、返金の可能性や具体的な対処法、そして被害を未然に防ぐための実践的な対策までをわかりやすく解説します。
すでに被害に遭ってしまった方も、まだ不安を感じている段階の方も、まずは正しい知識を持つことが第一歩です。
返金の可能性を高めるために必要な証拠や相談先の選び方、注意すべきポイントを今すぐ確認しましょう。
【仮想通貨詐欺の疑いがある方へ】
仮想通貨詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
返金は難しい?仮想通貨詐欺の特徴
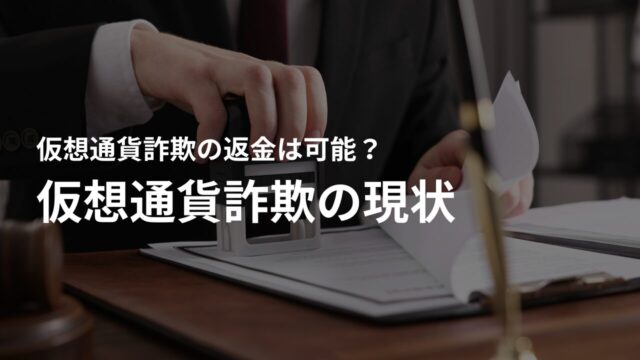
仮想通貨取引が一般化するにつれ、その仕組みを悪用した詐欺行為も巧妙化しています。
仮想通貨詐欺は、国境を越えた犯罪となるケースも多く、一度資金を奪われると追跡が難しいという特徴があります。
特に「億り人」などの成功事例が広まることで、「自分も大きく稼げるかもしれない」という心理に詐欺師たちは付け込んできます。
まずは詐欺の実態を知り、冷静な判断ができるようになることが重要です。
仮想通貨詐欺の主な手口と特徴
仮想通貨詐欺には様々な手口が存在しますが、いずれも「簡単に大金が稼げる」という人間の欲望に付け込む点で共通しています。
投資詐欺が最も典型的な手口であり、「仮想通貨だから」という理由で「高収益・高配当」「リスクゼロ」などと誇大広告し、実態のない投資話で資金をだまし取ります。
また、偽のウォレットサイトを装って個人情報を入力させるフィッシング詐欺や、新しい仮想通貨プロジェクトで大きな利益が得られると装い実態のないトークンを販売するICO詐欺も増加しています。
詐欺の典型的な特徴として、「過剰な利益を約束する」「元本保証を謳う」「運営者情報が不透明」「計画性が曖昧」「紹介制度がある」などが挙げられます。
これらの要素を含む投資話には要注意です。
近年では、SNSやマッチングアプリを通じた勧誘や、AIを使った著名人の偽画像・音声による勧誘など、手口も技術的に高度化しています。
仮想通貨詐欺は世界規模で問題に?
仮想通貨詐欺による被害は年々増加傾向にあります。世界的に増加している主な原因は、ロマンス詐欺の流行と、生成AIの台頭にあると言われています。
「豚の食肉解体(pig butchering)」と呼ばれるロマンス詐欺の増加と生成型人工知能(Generative AI)の利用拡大により、2024年の暗号資産(仮想通貨)詐欺による収益は過去最高を記録する可能性が高いと、米ブロックチェーン分析企業チェイナリシス(Chainalysis)が発表した。
2024年の暗号資産詐欺(仮想通貨詐欺)による収益は、少なくとも99億ドルから、124億ドルにものぼると言われています。
巧妙な手口で資産を奪う仮想通貨詐欺は、日本に限らず世界規模で問題になっているのです。
https://phamalaw.com/media/romancesagi-miwakekata/
https://phamalaw.com/media/ai-fraud/
「誰にも相談できない」人も多い仮想通貨詐欺
仮想通貨詐欺に限らず、投資詐欺などの被害に遭った人の中には、自責の念や「恥ずかしい」と思う感情から被害を隠してしまい、適切な相談や対応が遅れるケースも少なくありません。
「自分が騙されるはずがない」という思い込みが、被害の発見や対応を遅らせる原因にもなるのです。
経済的には、貯蓄を失うだけでなく、借金をして投資するケースも多く、生活基盤そのものが崩壊するリスクもあります。
このような深刻な影響を考えると、詐欺被害の予防と早期発見、そして適切な対応がいかに重要かがわかります。何より、家族や信頼できる人物、そして弁護士などの専門家に「相談」することが重要です。
弁護士への相談が二次被害を生むことも
仮想通貨詐欺は前述の通り、国境を越えた犯罪となるケースも多く、一度資金を奪われると追跡が難しいという特徴があります。
そのため、「弁護士に着手金を支払ったのに対応してもらえない」二次被害も懸念されます。
インターネット上には、投資詐欺や「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる手口の詐欺被害者などをターゲットに、弁護士が「返金を受けられる」などといって相談を募る多くのサイトや広告があります。
しかし、弁護士側に高額の着手金などを払ったのに、その後も適切に対応してもらえないといった、詐欺の“二次被害”ともいわれる事例が各地で相次いでいます。
二次被害をうむ弁護士には「必ず被害金を回収できる」など本来確約できないような約束をし、他方では相談者に対して十分な説明を行わない、といった特徴があります。
もし投資詐欺の加害者に対して法的措置を考えているのであれば、二次被害には十分注意しましょう。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
仮想通貨詐欺の返金確率は?返金が困難だといわれる理由を解説
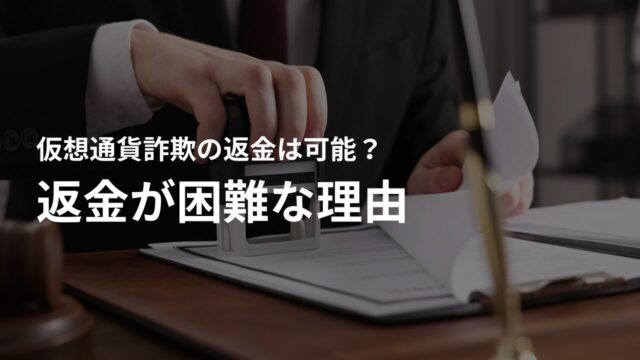
仮想通貨詐欺の被害に遭った場合、最も気になるのは「お金が戻ってくるのか」という点でしょう。
結論から言えば、返金の可能性はケースバイケースであり、返金確率を割り出すことは不可能です。場合によっては、返金ができないこともあります。
ただし、諦めずに適切な行動を取ることで、返金の確率を高めることは可能です。
特に初期対応の速さや証拠の質、専門家への相談など、被害者側の行動が返金成功の鍵を握っています。
仮想通貨詐欺は返金可能なのか
仮想通貨詐欺における返金の成功事例は、日本国内にも確かに存在します。場合によりますが、決して不可能ではありません。
一方で成功事例の多くは、詐欺師の特定ができたケース、国内の詐欺グループが関与していたケース、被害直後に素早く行動を起こしたケースなどに限られているという点に注意が必要です。
もし泣き寝入りすることなく法的措置をとりたいのであれば、詐欺が判明した瞬間から速やかに取引に関する情報など、あらゆる証拠を保存しておくのが良いでしょう。
https://phamalaw.com/media/cryptocurrency-fraud-bear-it/
仮想通貨詐欺の返金はなぜ難易度が高いのか
仮想通貨詐欺の返金を難しくする要因はいくつかあります。
前述した、仮想通貨の匿名性と追跡の難しさは最大の障壁です。
一度ブロックチェーン上で移動した資金は、技術的に追跡可能であっても、実際の所有者を特定することは容易ではありません。
また、国際的な法的管轄の問題も大きな障壁となります。
詐欺グループが海外に拠点を置いている場合、国際的な法執行の協力が必要となりますが、国によって法律や対応が異なるため、手続きが複雑化します。
法的手段が返金の可能性を高める?
難易度は高いものの、返金の可能性を高めることは可能です。仮想通貨詐欺の返金を目指す場合、主に以下の手段が考えられます。
まず警察への被害届の提出は基本的なステップです。詐欺は刑法246条に基づく犯罪であり、警察による捜査が行われる可能性があります。
ただし、警察は「民事不介入」の原則があり、詐欺師を逮捕しても返金請求までは行ってくれません。
国ごとの法律と仮想通貨詐欺への対応策
仮想通貨に対する法規制は国によって大きく異なります。日本では金融庁による暗号資産交換業者の登録制度があり、比較的厳格な規制が設けられています。
アメリカではSECやCFTCといった機関が仮想通貨詐欺に積極的に対応していますが、欧州やアジアの一部の国では規制の枠組みがまだ発展途上にあります。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
仮想通貨詐欺の返金を諦めてしまうケースは?
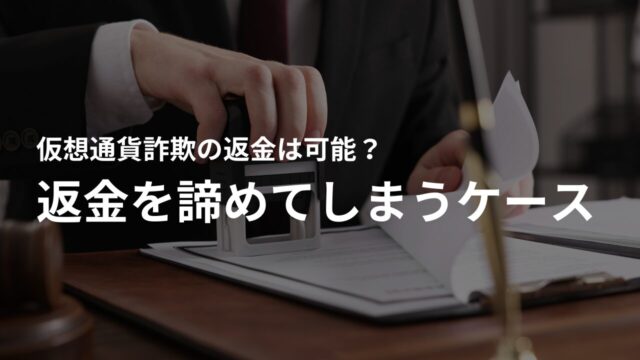
仮想通貨詐欺の返金を望んでも、多くの被害者が諦めてしまいます。その背景には、返金請求にかかる費用や手続きの複雑さ、詐欺師の特定困難、相談先の不明確さといった複数の要因が関係しています。
法的な返金手続きにかかる費用が高い
仮想通貨詐欺の返金を目指すには、弁護士や司法書士への相談料や着手金が必要です。
詐欺で資金を失った直後に、さらに費用を用意して返金手続きを依頼するのは、現実的に厳しいと感じる人が多い傾向にあります。
特に被害額がそれほど大きくない場合、かかる費用に対して回収できる金額が見合わないと判断し、返金請求自体を断念してしまうケースも見受けられます。
初回相談が無料の法律事務所もあるため、まずは費用をかけずに専門家に相談することが返金への第一歩です。
相談の結果、返金の可能性があると分かった時点で、改めて着手金の支払いを検討するのが効果的です。
詐欺師の情報がつかめず、返金請求ができない
仮想通貨詐欺では、加害者の身元や連絡先が不明なため、返金を求める対象すら特定できないことが少なくありません。
とくにSNSやウェブサイト経由の詐欺は、匿名性が高く、偽名や使い捨ての連絡手段が使われていることがほとんどです。
加えて、仮想通貨はブロックチェーン上で取引されるため、送金先を追跡するのも困難です。
わずかな手がかりでも、取引所の口座情報や送金履歴を専門家に提示することで、返金につながる可能性が出てきます。
詐欺師に関する情報が乏しくても、専門家の力を借りれば追跡可能な場合もあります。
どこに返金の相談をすべきか分からない
仮想通貨詐欺の被害者の中には、誰に返金の相談をすれば良いか分からず、対応を後回しにしてしまう人が多く存在します。
警察や消費者センター、金融庁、法律の専門家など相談先は多岐にわたりますが、それぞれの窓口が扱う領域が異なるため、適切な対応先を選ぶのが難しい状況です。
さらに、仮想通貨の仕組みに詳しくない相談窓口もあるため、正確な対応がなされないこともあります。
1つの相談窓口にこだわらず、複数の専門家や機関に意見を求めることで、返金の可能性を広げられます。
とくに法的な対応を考えている場合は、複数の弁護士に相談し、対応力を見極めることが重要です。
詐欺を裏付ける証拠が不足している
仮想通貨詐欺の返金を求めるには、被害の証明となる証拠の有無が極めて重要です。
しかし、詐欺師との会話履歴や送金記録が残っていないと、返金請求が認められない可能性が高くなります。
特にLINEやSNSのメッセージが削除されていたり、詐欺サイトが閉鎖されていると、証拠の確保が困難になります。
怪しいと感じた時点で、スクリーンショットや送金記録などを保存しておく習慣が大切です。
返金のためには、初期段階から証拠の蓄積を意識しておく必要があります。
被害に気付くまでに時間がかかってしまった
被害発覚から長期間が経過していると、返金のチャンスが著しく低下します。
詐欺師は早い段階で連絡手段を断ち、証拠を消すため、時間の経過は被害回復の障害になります。
また、法律上は損害賠償請求の時効も存在し、3年で請求権が消滅する可能性があるため、行動の遅れはリスクとなります。
返金の可能性を高めるには、被害に気づいた時点で迅速に専門家へ相談することが鍵です。
「様子を見る」という選択は、取り返しのつかない状況を招くおそれがあります。
海外業者が関与している詐欺は返金が難しい
海外の仮想通貨業者が関与する詐欺では、返金の手続きが国内案件と比べて格段に難しくなります。
国境を越える法的対応は、制度の違いや費用の増加など複雑な問題を伴うため、一般の被害者にとっては非常に高いハードルとなります。
さらに、日本国内では違法でも、詐欺行為が行われた国では合法とされているケースもあります。
海外の業者と取引を行う際は、信頼性を必ず確認し、不明点があれば専門家に事前相談することが不可欠です。
万一、海外詐欺に巻き込まれてしまった場合でも、国内の法律専門家に相談することで打開策が見つかることもあります。
仮想通貨詐欺への具体的な対処法・返金の手順
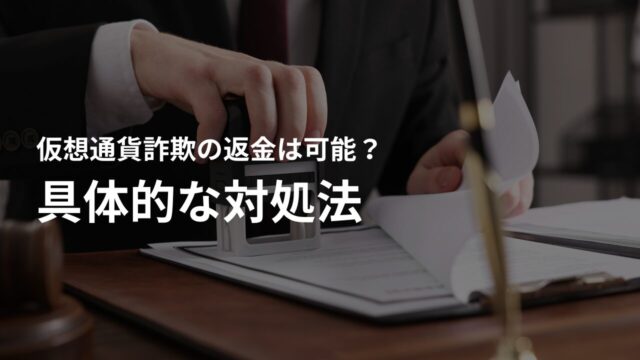
仮想通貨詐欺の被害に遭った場合、冷静かつ迅速な対応が求められます。
感情的になったり、詐欺師に直接交渉したりすることは避け、以下のステップに従って行動することが重要です。
特に証拠の収集と保全は、返金の可能性を高める上で最も重要なポイントとなります。
適切な専門家に相談しながら、組織的に対応を進めていきましょう。
速やかな証拠の保存
仮想通貨詐欺の被害に遭った場合、時間との勝負になります。
対応が遅れるほど、以下のような問題が発生し、返金の可能性は低下します。
まず、詐欺師は資金を素早く移動させ、追跡を困難にします。
また、証拠も時間の経過とともに消えていきます。
詐欺サイトやSNSアカウントは突然閉鎖されることが多く、重要な証拠が失われる可能性があります。
さらに、法的観点からも時間の経過はマイナスです。詐欺の時効を過ぎると、法的手段による返金請求が不可能になります。また、法的手段を講じるにしても、詐欺師の所在が不明になる可能性が高まります。
特に、詐欺師が「まだ儲かるかもしれない」と言って時間を稼ごうとする場合は要注意です。
これは詐欺の典型的な手口であり、時間稼ぎをしている間に資産を隠されてしまうリスクがあります。
仮想通貨詐欺から返金を目指すなら証拠の確保が必須
仮想通貨詐欺に巻き込まれたと気づいた時点で、返金の可能性を少しでも高めるには証拠を集めて保管することが不可欠です。
証拠が不十分だと、専門家に相談しても対応が難しくなる恐れがあります。被害に気づいた時から意識的に情報を残すことで、返金への道が開けます。
被害の金額や日時を具体的に記録する
仮想通貨詐欺に遭ったと認識したら、送金日時や金額、仮想通貨の種類などを正確に記録しましょう。
送金時の為替レートや、複数回にわたる被害がある場合は、それぞれの内容を時系列でまとめておくと有効です。
こうした基礎情報は、返金請求の全体像を把握するための出発点となります。
時系列のメモは、専門家との相談時にも話が通じやすくなります。
加害者や送金先に関する情報を集めて残す
勧誘者の氏名や連絡先、振込先の口座情報、利用したサイトのURLなどは、返金の根拠となる重要な証拠です。
これらの情報は詐欺師の特定につながるため、できる限り詳細に記録しましょう。
仮想通貨詐欺では加害者がすぐに姿をくらますことが多いため、気づいた時点で保存しておくことが必要です。
詐欺サイトの画面は閉鎖前にスクリーンショットを撮るようにしてください。
トランザクションID(TxID)や取引履歴を保存する
仮想通貨の送金にはトランザクションID(TxID)という取引の識別子が付与されます。
このIDを使えばブロックチェーン上で取引履歴を確認でき、返金のための資金追跡に役立ちます。
取引所のアカウント情報や送金記録、取引画面のスクリーンショットなども合わせて保存しておくとさらに効果的です。
TxIDを記録しておけば、専門家による資金調査の糸口になります。
詐欺師とのやり取りを保存しておく
詐欺師とのメッセージや通話の内容も、詐欺の事実を証明する上で欠かせない証拠です。
LINEやSMS、SNSでの会話の中には、送金の指示や投資に関する虚偽の説明が含まれていることがあり、返金を求める根拠となります。
やりとりのスクリーンショットは、発言の流れが分かるように連続で保存するのが望ましいです。
画面キャプチャでは、日付・時間の表示も一緒に記録しておきましょう。
住所や所在地が分かるなら必ず控える
詐欺師や関連事業者の住所情報が判明している場合、それは返金や法的手続きの上で非常に有力な情報になります。
企業のサイトや書類、契約内容などから住所を把握できた際は、正確に控えておいてください。
内容証明の送付や訴訟の際に必要となるケースもあります。
所在地が本当に存在するか、Googleマップなどで確認するのも効果的です。
被害に遭ったらどこに相談するべき?
仮想通貨詐欺の被害に遭った場合、以下の機関に相談・報告することが重要です。
それぞれの機関に適切な情報を提供することで、返金の可能性を高めることができます。
警察への被害届提出は最初のステップです。
最寄りの警察署に被害届を提出し、詐欺の詳細な状況と証拠を提示します。警察は事件として立件するかどうかを判断し、捜査を開始する可能性があるので、無駄にはなりません。
警察に相談する際は、詐欺師との全てのやり取り、送金の記録、詐欺サイトのスクリーンショットなど、できるだけ多くの証拠を準備しましょう。具体的かつ詳細な情報を提供することで、捜査の優先度が上がる可能性があります。
次に、消費者庁や金融庁の窓口にも相談しましょう。
消費者ホットライン(188)や国民生活センターはもちろん、金融サービス利用者相談室でも、仮想通貨詐欺に関する情報提供を受け付けています。
同様の被害が多数報告されている場合、組織的な対応が行われる可能性があります。
また、被害額が大きい場合や、法的手段を検討する場合は、早い段階で弁護士への相談も重要です。
特に仮想通貨や詐欺被害に詳しい弁護士を選ぶことで、より効果的なアドバイスを受けることができます。
具体的な返金までの手順を解説!
下記内容はあくまでも一例です。 個別の事案ごとに状況が異なり、最適な手段も変わってきますので、具体的な対応を検討する際は、必ず弁護士などの専門家に相談してください。
- 内容証明とは?
発送した手紙の内容と発送日を公的に証明できる制度で、後の裁判などで「いつ、どのような請求を行ったか」を示す有力な証拠となり得ます。 - 送付先の把握が重要
詐欺関与者(首謀者・勧誘者・資金移動に協力した者など)を正確に把握し、責任追及が可能な範囲で送付することが望ましいです。実際には関係者の特定が困難な場合もあるため、事前に弁護士や調査会社などと相談しながら行うとよいでしょう。 - 弁護士経由で送付するメリット
弁護士名義の通知書は、相手に「法的手段を検討している」という強い意思を伝えられます。ただし、送付だけで必ず返金を得られるわけではありませんので、あくまでも「返金を求める第一段階」と認識してください。
- 証拠の整理と提示
詐欺の事実を示す資料(契約書や送金履歴、メッセージのやり取りなど)を整理し、相手に明確に「これだけの証拠がある」と示すことが重要です。 - 記録を残すことの重要性
交渉過程での相手の発言ややり取りは、可能な限り録音やメール・書面などで保存しましょう。曖昧な口頭合意や根拠のない返金計画に流されないよう注意が必要です。 - 合意書の締結
返金金額や支払方法・期限などが明確に示された合意書を締結することで、後のトラブルを防げます。合意が難航する場合には、速やかに次のステップを検討しましょう。
- 詐欺加害者が時間稼ぎをする可能性
「もう少し待てば利益が出る」「手続きに時間がかかる」などと先延ばしを図る詐欺業者も多く、被害回復が遅れる原因となります。 - 主張の根拠と請求の種類
一般的には、民法上の「不法行為」に基づく損害賠償請求が考えられます。また、場合によっては「不当利得返還請求」や「契約関係に基づく損害賠償請求」を主張することも。実際には事案ごとに適切な主張を検討する必要があるため、弁護士のサポートが有益です。
- 刑事告訴の意義
刑事事件として受理され捜査が進めば、加害者に対する社会的・法的圧力が高まり、結果として返金に応じるケースもあります。ただし、刑事手続きはあくまで「犯罪事実の捜査と処罰」が目的であり、直接的に金銭回収を保証するものではありません。 - 告訴の受理はケースバイケース
警察が告訴状を受理するかは事件の内容や証拠の状況次第です。証拠不十分などを理由に捜査が進まない可能性もあるため、早期に弁護士へ相談し、証拠を整理しておくことが大切です。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
仮想通貨詐欺を未然に防ぐ方法
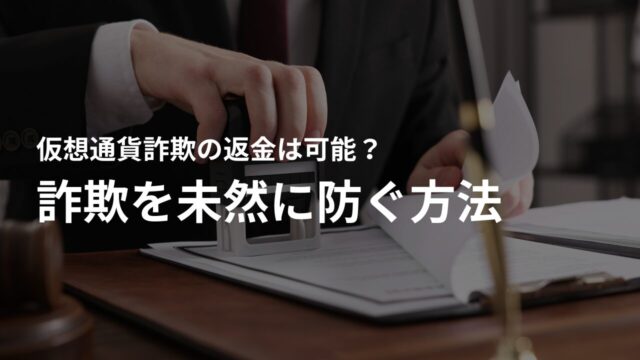
仮想通貨詐欺の被害に遭わないための最善の策は、事前の予防です。
以下のチェックポイントを参考に、怪しい投資話や取引には慎重に対応しましょう。
特に「簡単に儲かる」「元本保証」といった甘い言葉には要注意です。
仮想通貨投資には必ずリスクが伴うことを認識し、冷静な判断を心がけることが重要です。
信頼できる取引所とウォレットを選ぶ
仮想通貨を扱う際、取引所やウォレットの選択は安全性を左右する重要なポイントです。
まず、日本国内で仮想通貨取引を行う場合、金融庁に登録された取引所を選ぶことが基本です。
金融庁のウェブサイトでは、正規に登録された事業者のリストを確認できます。
未登録の取引所や海外の取引所を利用する場合は、特に注意が必要です。
ユーザーレビューやセキュリティ対策の実績、運営企業の透明性などを徹底的に調査してから利用するようにしましょう。
ウォレットに関しては、ハードウェアウォレットが最も安全性が高いとされています。
オフラインで仮想通貨を管理できるため、ハッキングのリスクを大幅に減らすことができます。
また、二段階認証の設定や、定期的なパスワード変更など、基本的なセキュリティ対策を徹底することも重要です。
大きな取引を行う前には、少額で送金テストを行うなどの慎重さも必要です。
詐欺の兆候を知っておく
仮想通貨詐欺を見破るためには、典型的な「詐欺の兆候」を知っておくことが重要です。
過剰な利益の約束は最も明確な警告サインです。
「毎月100%の利回り」「確実に儲かる」といった表現は、ほぼ間違いなく詐欺です。
正当な投資では、このような非現実的な利益を保証することはありません。
また、「期間限定」「今だけ特別」といった緊急性を煽る文言にも要注意です。
これは冷静な判断を妨げるための手法であり、詐欺の典型的な特徴です。投資の判断を急がせるような状況では、特に慎重になる必要があります。
運営者の情報が不透明なプロジェクトも危険信号です。
正規のプロジェクトでは、チームメンバーの経歴や実績が公開されているのが一般的です。
「匿名の天才プログラマー」などの曖昧な説明しかないプロジェクトには関わらないようにしましょう。
また、ホワイトペーパーの内容も重要なチェックポイントです。
専門用語が羅列されているだけで具体的な技術説明がない、ロードマップが非現実的である、などの特徴がある場合は詐欺の可能性が高いです。
セキュリティ対策を万全に
仮想通貨を安全に管理するためには、いくつかの基本的なセキュリティ対策が必要です。
強固なパスワード設定と二段階認証は最低限の対策です。
特に取引所やウォレットへのアクセスには、他のサービスとは異なる複雑なパスワードを使用し、可能な限り二段階認証を設定しましょう。
また、仮想通貨関連の情報をSNSで公開することは避けるべきです。
保有している仮想通貨の種類や量を公開することで、攻撃者のターゲットになる可能性があります。
大量の仮想通貨を取引所に保管しておくことも危険です。
長期保有する仮想通貨は、ハードウェアウォレットなどのコールドストレージに移しておくことをおすすめします。
「取引所はハッキングされる可能性がある」という前提で行動するのが安全です。
さらに、定期的なソフトウェアの更新や、信頼できるセキュリティソフトの使用も重要です。
多くのマルウェアが仮想通貨の窃取を目的としているため、基本的なセキュリティ対策が資産を守る上で大きな役割を果たします。
フィッシング詐欺・マルウェア対策も重要
仮想通貨詐欺では、フィッシング詐欺やマルウェアを使った手口も増加しています。
フィッシング詐欺では、正規の取引所やウォレットサービスを装ったメールやウェブサイトを通じて、ログイン情報を盗み取ろうとします。
URLをよく確認し、不審なリンクはクリックしないようにしましょう。
また、取引所やウォレットのサイトにアクセスする際は、ブックマークからアクセスするか、URLを直接入力することをおすすめします。
検索エンジンの結果から偽サイトにアクセスしてしまうケースもあります。
マルウェアに関しては、不審なファイルのダウンロードやアプリのインストールを避けることが基本です。
特に、仮想通貨関連の無料ツールなどを謳う不審なソフトウェアには注意が必要です。
また、公共Wi-Fiや安全性が確認できないネットワーク上での仮想通貨取引は避けるべきです。
可能な限り、自宅の安全なネットワーク環境で取引を行いましょう。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
まとめ
仮想通貨詐欺は技術の進化とともに複雑化・巧妙化していますが、基本的な注意点を押さえておくことで、リスクを大幅に減らすことが可能です。
被害に遭わないための予防策、そして万が一被害に遭った場合の対応について、しっかりと学習しておきましょう。
常に新しい情報にアンテナを張り、冷静な判断を心がけることが最も重要です。
また、仮想通貨の返金は困難ですが、弁護士に相談することで可能性を高めることができます。
もし被害にあった際は、弁護士への相談も検討しましょう。
【仮想通貨詐欺の疑いがある方へ】
仮想通貨詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。
当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。
当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。
当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。
本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。