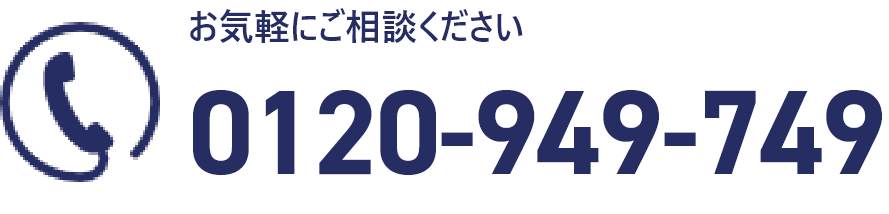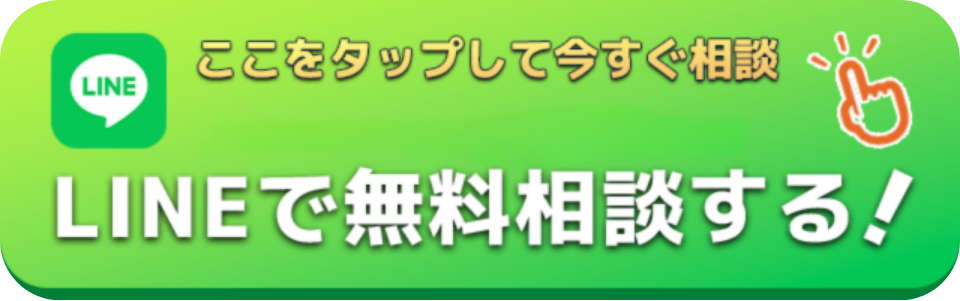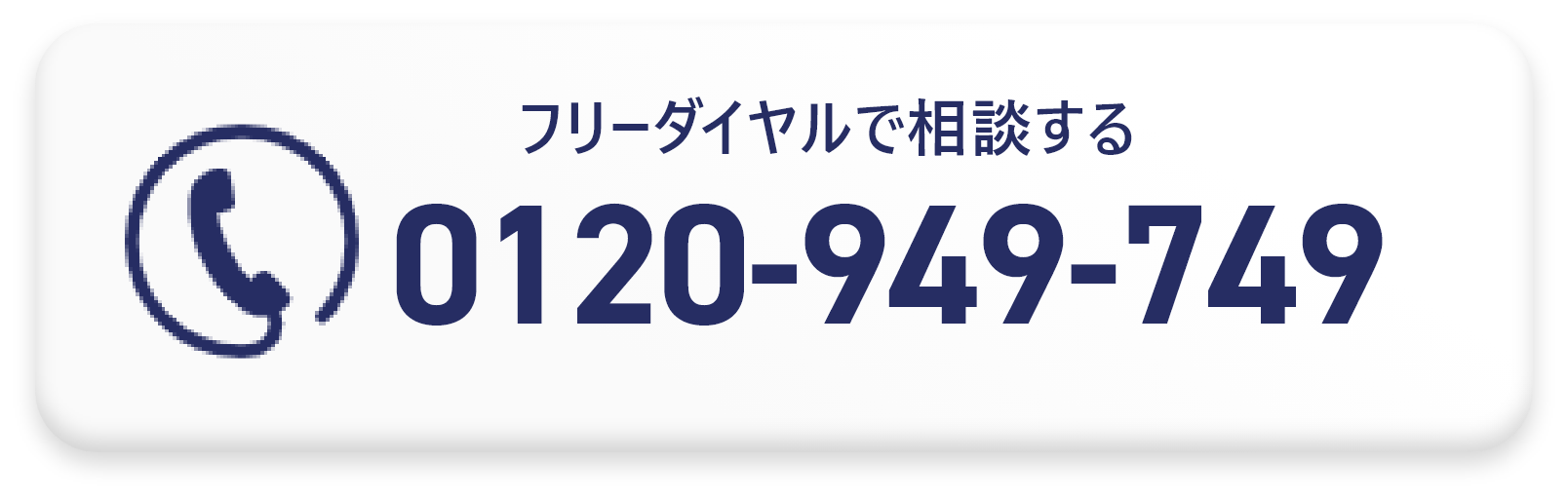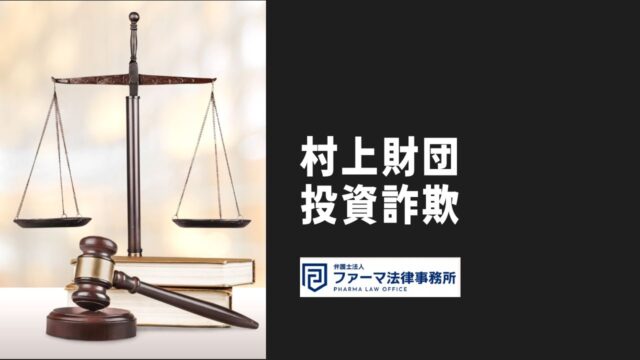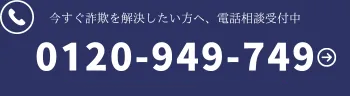副業ブームの波に乗り、多くの人が「簡単に稼げる」とうたう情報商材に手を出しています。
しかし、その中には粗悪な内容や詐欺まがいの商材も含まれており、トラブルが多発しています。
本記事では、情報商材が「なぜ悪い」と言われるのか、その背景や種類、リスク、そして購入後の対処法までを詳しく解説します。
被害を未然に防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください
【情報商材詐欺の疑いがある方へ】
情報商材詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
そもそも情報商材とは?概要と種類を正しく理解しよう
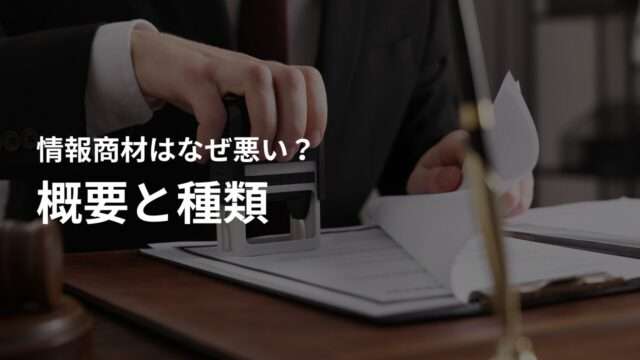
「情報商材」とは、その名の通り「情報」を商品として販売するものを指します。
販売される情報のジャンルや形式は多岐にわたり、動画やPDF、オンラインセミナーなどが一般的です。
情報そのものが商品となるため、評価は購入者の知識や目的に依存し、実際の価値判断は難しい面があります。
まずは、代表的な情報商材の種類と、その特性を正しく理解していきましょう。
なぜ悪いイメージが付きまとうのか
情報商材には「詐欺的」「怪しい」といった負の印象が根強くあります。
その原因のひとつは、内容の質と価格が極端に見合っていないケースが多いことです。
また、販売者がSNSや広告で「誰でも簡単に稼げる」といった誇大表現を使うため、実際の効果とのギャップにより不信感を持たれます。
加えて、返金に応じない業者も多く、被害者の声が増加している現状がネガティブな印象を強めています。
投資系の情報商材(株式、FX、保険、仮想通貨、不動産)
投資分野の情報商材は、「資産を増やすノウハウ」を謳って高額販売される傾向があります。
株式やFXに関するものは特に多く、中にはプロ顔負けの知見を語るものも存在しますが、裏付けのない情報や過去の一時的成功例を過度に強調したものも少なくありません。
仮想通貨や不動産に関しても、変動リスクが高いにもかかわらず、「絶対に儲かる」と誤解を招く表現で販売されることが問題視されています。
こうした商材に手を出す際は、その情報の出所と根拠を厳しくチェックする必要があります。
コンプレックス・悩み解決系の情報商材
ダイエットや薄毛、恋愛・結婚などの悩みに訴えかける情報商材もあります。
こうした商材は購入者の感情に強く働きかけることで購買意欲を引き出すのが特徴です。
「〇日で痩せる方法」「〇週間でモテ体質に」など、科学的根拠に乏しい誇大表現が使われることが多く見られます。
そのため、悩みを抱えた人ほど冷静な判断ができず、高額な商品を購入してしまうリスクが高まります。
内容があまりに抽象的なものには注意が必要です。
目標達成系の情報商材
「夢を叶える」「収入を10倍にする」など、自己啓発やモチベーションに関する商材も人気です。
しかし、こうした情報の多くは抽象的な精神論に終始しているケースが目立ちます。
中には具体的な手法やステップが示されていないまま、「ポジティブに生きよう」といったメッセージだけが繰り返される商材も存在します。
成功事例として著名人の名前を挙げることもありますが、再現性のない話に過ぎないことが多い点に注意が必要です。
ギャンブル必勝系の情報商材
パチンコや競馬、オンラインカジノの攻略法をうたう情報商材も一定の需要があります。
「必ず勝てるロジック」や「高確率で的中する予想」といった表現は、根拠が不明確で違法性も疑われます。
とくに公営ギャンブルにおいては、確実性を保証するような販売は法律に抵触する可能性もあります。
ギャンブル依存の傾向がある人は、過大な期待を持ちやすいため、冷静な判断が難しくなる点でも危険です。
副業系の情報商材
近年急増しているのが「スマホ1つで月収〇万円」といった副業系情報商材です。
アフィリエイトや物販、自動収益化を謳うものが多く、「簡単に稼げる」との誘い文句でSNSから集客されています。
しかし、実際にはまともに稼げない内容であることが多く、マニュアル通りにやっても収益ゼロという声も少なくありません。
また、「再現性が高い」との記述がある一方で、実際の稼ぎは極めて限定的です。
慎重にレビューを確認することが求められます。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
情報商材が悪質とされる理由
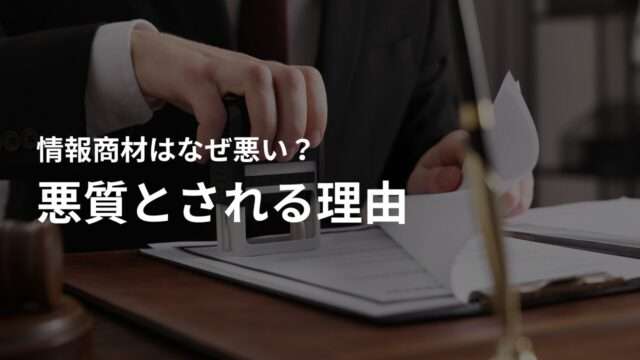
情報商材には、有益な情報を提供する正当なものも存在します。
しかし現実には、質の低い内容や返金に応じない業者などが多く、結果的に「悪質」「詐欺的」といった印象が定着しています。
このセクションでは、情報商材が悪質とされる具体的な理由について解説します。
粗悪な内容の情報商材が多い
情報商材の中には、中身がほとんど空っぽの粗悪なものが多数存在します。
たとえば、「〇〇するだけで稼げる」といった宣伝に期待して購入したところ、実際は抽象的な内容しか書かれておらず、行動に移せる情報が一切なかったというケースが報告されています。
さらに、他サイトからの転載や無料ブログのまとめといった、独自性に乏しい内容を高額で販売する例も後を絶ちません。
このような実態が、情報商材に対する信用を著しく損ねています。
情報の価値は購入者の知識によって変動しますが、明らかに金額に見合わない内容は「悪質」と判断される原因となります。
価格と提供価値の不均衡
多くの情報商材では、価格と提供価値が著しく乖離しています。
数万円〜十数万円を超える価格に対し、実際に提供されるのはPDF数ページ程度の内容ということも珍しくありません。
しかも、その内容が誰でも知っている常識的な情報であれば、購入者にとっては「詐欺に遭った」と感じるのも無理はないでしょう。
本来、高額な情報商材であれば、専門的な知見や再現性の高いノウハウが期待されるべきです。
しかし、現実にはそうした内容が提供されるケースはごく一部に限られます。
購入前には、レビューや比較サイトなどを通じて、価格に対する妥当性を冷静に判断する姿勢が不可欠です。
返金対応を拒否する業者の存在
悪質な情報商材業者の多くは、「返金保証あり」としながらも実際には返金に応じません。
「規約違反」や「一定期間内での申請が必要」といった名目で、返金請求を却下するケースが相次いでいます。
中には、問い合わせに一切応じない、または連絡手段を絶つ業者も存在します。
このような対応を取る業者が多数を占める現状が、情報商材全体のイメージを悪化させている要因です。
返金保証が明記されていても、実際に返金されるかどうかは全く別の問題であると認識することが重要です。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
情報商材の購入者はどのような心理状態?
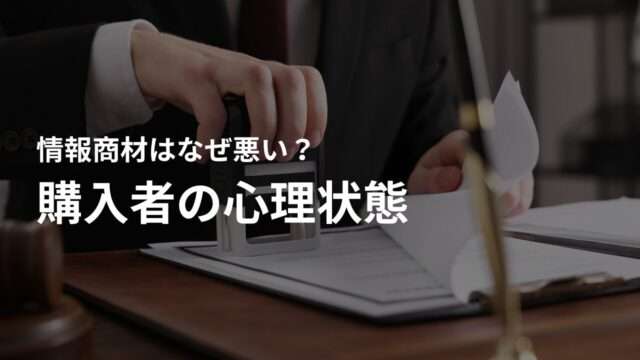
情報商材を購入する人々の背景には、単なる無知だけでなく、心理的な要因が深く関係しています。
「楽に稼ぎたい」「成功者のようになりたい」といった願望が、冷静な判断力を鈍らせてしまうのです。
このセクションでは、情報商材に引き寄せられる心理的メカニズムを解説します。
「簡単に稼げる」誘惑への弱さ
「1日数分の作業で〇万円」「誰でもすぐに稼げる」といった言葉は、非常に魅力的です。
こうしたキャッチコピーは、努力せず結果だけを求めたいという心理を巧みに突いてきます。
特に、収入に不安を感じている人や副業を探している人は、「今すぐ成果を出したい」という焦りから、判断力が鈍る傾向があります。
「最初だけ頑張れば、あとは自動で収入が入る」といった希望的観測が、購入という決断を後押ししてしまうのです。
しかし、現実には楽して稼げる仕組みなど存在せず、その落差が「詐欺にあった」という被害感情に繋がります。
成功事例の過大評価
情報商材の多くは、「実際に稼げた人の声」として成功体験談を前面に出しています。
「月収100万円突破」「一週間で会社員以上の収入に」などのフレーズは、強力な説得力を持ちます。
しかし、その多くは演出されたものであったり、ごく一部の例外的成功に過ぎません。
それにもかかわらず、購入者は「自分も同じように成功できるはず」と思い込んでしまいます。
この認知の歪みこそが、冷静な判断を妨げ、過度な期待による購入行動につながるのです。
実際に結果が出ないと「騙された」と感じるのも当然でしょう。
繰り返し購入することで「ファン化」してしまう
情報商材の販売者は、ただの「売り手」ではなく、カリスマ的な発信者として振る舞うことがあります。
購入者は徐々にその発信者を信頼し、「ファン」として商材を次々と購入するようになります。
これは単なる消費行動ではなく、心理的な帰属欲求や依存にも近い現象です。
発信者が「これは次のステップに必要」と言えば、その言葉を疑うことなく信じてしまう構造が生まれます。
こうしたファン化は、金銭的損失だけでなく冷静な判断力の喪失というリスクも伴います。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
知っておくべき情報商材の巧妙な販売手口
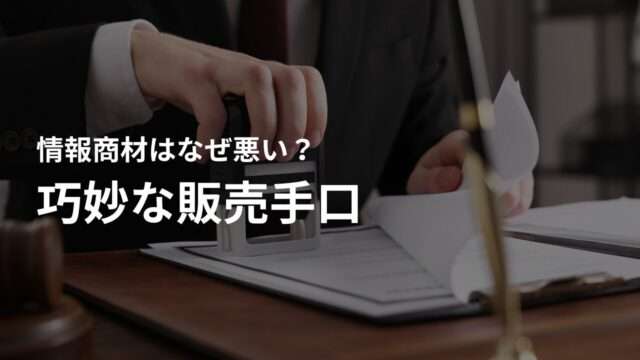
情報商材は、単にウェブサイトで販売されるだけではありません。
販売者たちは、より自然に・より信頼を抱かせる手法でターゲットに近づきます。
このセクションでは、主な4つの販売ルートとその具体的な勧誘方法を解説します。
知っていれば避けられるリスクも多いため、ぜひ事前に確認しておきましょう。
インターネット上の広告
多くの情報商材は、派手で目を引くネット広告を使って集客します。
「スマホを1回タップするだけで日収〇万円」「主婦が副業で月100万円」など、現実離れした文句が並びます。
こうした広告は、GoogleやSNS広告に掲載され、興味を引いた人をランディングページへ誘導するのが基本パターンです。
ページでは、さらに興味をそそるストーリー仕立ての動画や体験談が続き、購入ボタンへと誘導されます。
特に問題なのは、動画に出てくる人物や成功談が架空であることが多く、事実と異なる情報が堂々と使われている点です。
メールやSNSで売り込む
最近では、メールアドレスやSNSアカウントを通じた直接勧誘型の営業手法が増えています。
SNSの広告や投稿から興味を持った人に対し、LINEやインスタDMでメッセージを送り、個別にやり取りする中で商材を紹介するスタイルです。
「あなたにだけ特別」「今だけ特典付き」などの限定感を演出し、購入を即す傾向があります。
また、返信のしやすさや親近感を感じやすいため、警戒心が薄れやすい点がリスクです。
実際には複数人に同じ文面を送っているだけのテンプレ営業であることがほとんどです。
対面で直接売買される
一部の情報商材は、セミナーや交流会の場で対面販売されるケースもあります。
「無料説明会」や「起業相談会」などの名目で人を集め、終盤に高額な情報商材を紹介する流れです。
対面での勧誘は説得力があり、その場の雰囲気や周囲の空気に流されて断れず購入してしまう人が多くいます。
中には、その場で申込書を書かせ、クレジットカード決済まで行わせるような強引な手法もあります。
このような場合、クーリングオフが適用される可能性もあるため、冷静な対応が求められます。
電話での販売勧誘
情報商材の中には、電話を使って購入を促すタイプのものも存在します。
過去にメールアドレスを登録したユーザーや、資料請求をした人を対象に電話をかけ、個別に説明を行います。
電話では、契約に必要な説明を省略されたり、聞き取りにくい内容を早口で伝えられたりすることもあります。
また、「今だけこの価格」「決断が早ければ成功も早い」といった心理的プレッシャーをかけてくることが多いため、焦って契約してしまわないよう注意が必要です。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
SNSを利用した情報商材詐欺
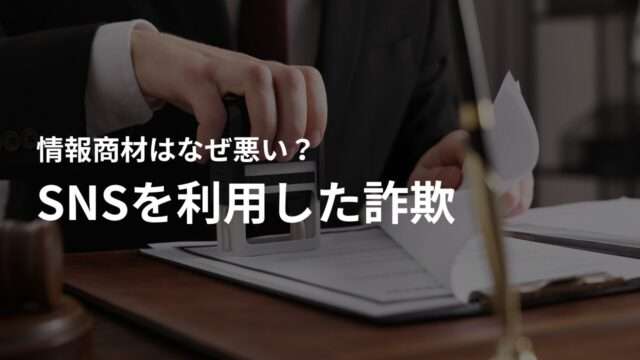
SNSの普及により、情報商材の勧誘方法はますます巧妙化しています。
特に若年層や副業志向の強い層がターゲットとなりやすく、日常的に使うSNSが詐欺の温床となっています。
このセクションでは、SNSを活用した主な詐欺手口を解説し、注意すべきポイントを明らかにします。
SNS広告を利用した誘導
InstagramやYouTube、TikTokなどのSNS広告は、視覚的に訴える情報商材の訴求に非常に適しています。
「稼げた人の体験談」や「豪華な生活風景」の動画が多く使われ、憧れを刺激するように設計されています。
投稿内容は、「この動画を見たあなたは選ばれた人です」といった限定感や優越感を与える演出が多く、気がつけばLINEや専用サイトに誘導されているケースが一般的です。
実際には、多くの動画が事実無根のシナリオで制作され、出演者もアルバイトや架空人物であることが少なくありません。
個別メッセージでの勧誘
SNSでフォローやいいねをされたあと、個別にDMが送られてくる勧誘パターンも頻発しています。
「今のままで満足していますか?」「人生を変えたいと思いませんか?」といった言葉で興味を引き、無料相談や説明会へと誘導される流れです。
会話が進むにつれ、「あなたなら成功できる」「この情報はあなたにだけ教える」と持ち上げられ、徐々に購入意欲を高められます。
このようなメッセージは心理的な隙をつくために緻密に設計されており、冷静な判断力を奪います。
LINEグループやZoom説明会による囲い込み
LINEグループやZoomを活用した情報商材の囲い込みは、近年とくに増加しています。
まず、LINEで「稼げるコミュニティ」に招待され、日々の投稿や成果報告により期待感が高められます。
次にZoom説明会が開催され、「この場に来たのは運命」「仲間と一緒に成功しよう」といった言葉で団結感を演出。
その空気感に流されて高額な情報商材に申し込んでしまうケースが後を絶ちません。
実際には、すでにシナリオが用意されており、参加者はターゲットとして順番にクロージングされていく仕組みです。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
情報商材のトラブルを避ける6つの方法!
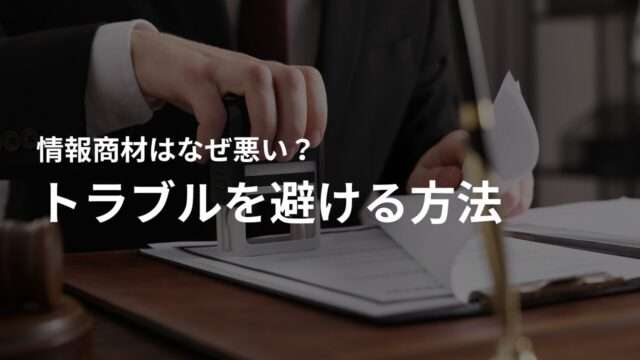
情報商材には、詐欺まがいの商品が多く存在するため、購入前に注意点を把握しておくことが重要です。
このセクションでは、被害に遭わないために実践できる6つの具体的な方法を紹介します。
少しでも不安を感じた場合は、購入を控える判断が、結果的に自分を守る手段になります。
紹介制度を使わない
情報商材の中には、「紹介された人だけが購入できる」という特別感を演出した販売手法があります。
この紹介制度は、マルチ商法と似た構造を持ち、商品そのものではなく「紹介報酬」を目的とした勧誘が横行しています。
「この人に紹介してもらったから安心」と思い込みやすく、冷静な判断を妨げる要因になります。
紹介があることで、かえって疑うべきポイントが見えなくなる危険性があるため、紹介制度を理由に安心するのは禁物です。
無料の講習会には行かない
「無料」とうたわれる講習会の多くは、最終的に高額な情報商材への勧誘が目的です。
会場では成功者の話や派手な演出で気分を高められ、判断力を失ったまま契約書にサインさせられる事例が多数報告されています。
「今しかない」「この場限り」といった言葉でプレッシャーをかけ、冷静な判断をさせないのが常套手段です。
無料だからと気軽に参加するのではなく、最初から断る姿勢がリスク回避につながります。
購入者のレビューは必ずチェック
情報商材を検討する際は、必ず実際の購入者のレビューを確認してください。
ただし、販売者が自作自演で高評価レビューを投稿しているケースもあるため、複数のサイトやSNSを横断的に調査することが重要です。
「誰が書いたか」が明らかでない匿名レビューは特に注意が必要です。
また、レビューに明らかな誇張や共通の文言が多い場合は、やらせの可能性を疑いましょう。
購入後のサポート体制
良質な情報商材であれば、購入後も学びを継続できるサポート体制が整っています。
問い合わせに迅速に対応したり、定期的なフォローアップが行われたりする場合は、一定の信頼性が期待できます。
反対に「売って終わり」の対応を取る業者は、詐欺的な体質である可能性が高いといえます。
購入前に、「どのようなサポートがあるのか」「連絡手段はあるのか」を確認しておくことが肝心です。
誇大広告か否か
「絶対に儲かる」「1日5分で月収100万円」などの文言は、すべて誇大広告と見なすべき表現です。
将来の成果を断定的に語る広告は、景品表示法に抵触する可能性があり、信用性の低い販売者である証拠とも言えます。
このような宣伝文句に引き寄せられる前に、「本当にそれが実現可能なのか」を冷静に考える癖をつけましょう。
特商法の記載事項の有無
特定商取引法(特商法)に基づき、通信販売では販売元の氏名・住所・連絡先・販売価格などの表記が義務付けられています。
この表記が曖昧だったり、記載がない商材は、法律に違反している可能性があるため購入を避けてください。
また、特商法の記載事項が明記されていたとしても、虚偽情報であることもあるため、記載内容に疑問があればネット検索などで実在性を確認しましょう。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
情報商材詐欺に遭わないための5つの対策
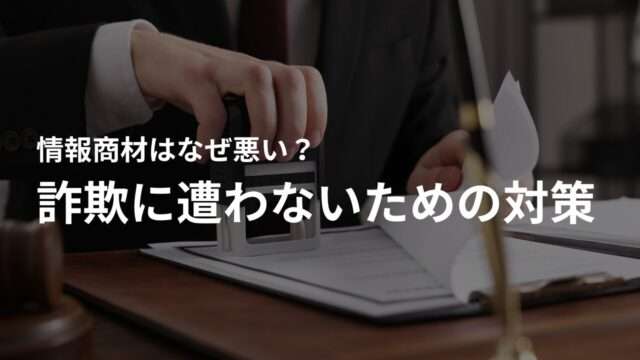
情報商材の詐欺被害は、事前のチェックで回避できるケースが多くあります。
このセクションでは、購入前に行っておくべき5つの実践的な対策を紹介します。
それぞれの行動が、被害を未然に防ぐ確かな盾となるでしょう。
販売者の情報を徹底的に調査する
まず行うべきは、販売者に関する情報の徹底的なリサーチです。
SNSでの発信傾向、企業ホームページの有無、代表者名や過去の評判を確認しましょう。
とくに「豪華な生活アピール」ばかりが目立つアカウントは注意が必要です。
信頼できる販売者であれば、無料で提供している情報も有益である傾向があります。
信頼性のあるレビューサイトを横断的に確認する
情報商材の購入を検討する際は、レビューを1サイトで判断せず、複数サイトで比較検討してください。
また、SNSや掲示板、Q&Aサイトなども活用して、実際の被害報告がないかも確認しましょう。
口コミがあまりに統一されすぎている場合は「自作自演」の可能性もあるため注意が必要です。
返金対応やクーリングオフ条件を確認する
商材の購入前には、返金保証の有無やクーリングオフの条件を必ず確認してください。
一見「返金保証付き」と書かれていても、実際には複雑な条件を満たさないと対応されないこともあります。
契約時の画面ややり取りの記録を保存しておくことが、トラブル時の証拠として有効です。
SNS広告やDMの手口を知っておく
情報商材の多くは、SNS広告やDMによる誘導が入り口となっています。
「今だけ限定」「あなたにだけ教える」といった言葉に惑わされず、その背後にある販売導線を見抜く力が重要です。
Zoom説明会やLINEグループでの囲い込みといった手口は、詐欺の常套手段として確立されています。
これらの手口を事前に知っておくだけで、警戒心が大きく高まります。
5.少しでも不安があれば「買わない」という判断をする
最も有効な対策は、「迷ったら買わない」という判断です。
不安や違和感を覚えた時点で、その直感は無視してはいけません。
販売者は購入を促すために、限定性や希少性を強調することがありますが、それに乗せられず一度立ち止まりましょう。
情報商材は慎重に選ぶ必要があり、「買わない勇気」が最善のリスク回避策です。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
情報商材はクーリングオフできるのか
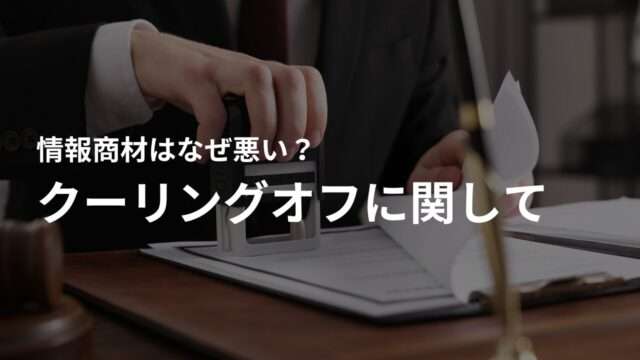
情報商材は詐欺的な内容でも、特性上「詐欺」として扱うのではなく、クーリングオフによる返金という形で決着がつく場合が多いです。
情報商材を購入してしまったあと、「やっぱりやめたい」「怪しいと気づいた」という場合、クーリングオフ制度の活用が検討されます。
この制度は条件次第で適用可能ですが、情報商材の販売方法によっては対象外となるケースもあります。
ここでは、クーリングオフの対象条件と、適用できない場合の対処法を確認していきましょう。
条件を満たせば、クーリングオフ可能
クーリングオフ制度は、特定の販売形態に該当する取引であれば、契約書面を受領した日から一定期間内であれば無条件でキャンセルが可能です。
情報商材でも、たとえば訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は8日、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引に該当すれば20日以内であればクーリングオフが認められます。
契約日は「契約書面を受け取った日」が基準となるため、手続きの際には日数計算に注意しましょう。
販売者が制度の存在を隠すケースもあるため、自身で正確な情報を確認することが重要です。
情報商材をクーリングオフできないときは?
情報商材を購入したものの、特定商取引法上のクーリングオフ対象外で、解約できない場合があります。
このときでも、販売者が重要な事実を告知せず契約させた場合や、誇大広告によって誤認させた場合には、消費者契約法等を根拠に取り消しを主張できる可能性があります。
困ったときは早めに消費生活センターや弁護士へ相談し、証拠資料を整えることが重要です。また、支払いや返金に関する証拠(契約書やメール、振込明細など)を確保しておくことも有用です。
クーリングオフの手続きで気をつけるポイント
クーリングオフを行う際には、記録が残る方法で通知する必要があります。
はがきや手紙、内容証明郵便など発送日が証明できる方法や、メールなどの電子手段を用いる場合もあります。
さらにクーリングオフであること、また「契約を解除する」「返金を求める」旨を明記し、日時や商品名、契約者情報を添える必要があります。
また、クレジット決済を利用している場合は、カード会社にチャージバック(決済停止)を申請する方法も併用するとよいでしょう。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
買ってしまったら、詐欺にあってしまったら
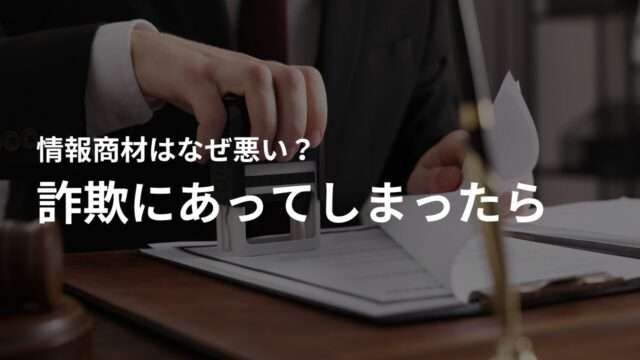
すでに情報商材を購入してしまった、あるいは詐欺の可能性があると感じている場合でも、適切な行動を取れば被害回復の可能性はあります。
本セクションでは、相談先や具体的な対処手段について解説します。
ひとりで悩まず、専門機関を積極的に活用しましょう。
消費者センターに相談する
まず最初の相談先として有効なのが、各地の消費生活センターや国民生活センターです。
情報商材に関するトラブルには慣れており、クーリングオフの可否や返金交渉の進め方など、具体的なアドバイスを受けられます。
無料で利用できる点も大きなメリットです。
電話やウェブフォームから簡単に相談できるため、「詐欺かも」と感じた時点ですぐに連絡しましょう。
相談内容は守秘義務のもとで扱われるため、安心して情報を共有できます。
弁護士に相談する
詐欺の可能性が高く、販売者とのやり取りで進展がない場合は、弁護士への相談が有効です。
とくに被害額が高額である場合や、複数回購入してしまったケースでは、法的手段を通じて返金を求めることが現実的です。
費用が不安な方には、法テラスを利用することで無料法律相談を受けることも可能です。
専門家のアドバイスに基づいて対応すれば、返金の成功率は大きく向上します。
クーリングオフできるか確認する
契約日や販売形態によっては、まだクーリングオフが可能なケースもあります。
自分で判断できない場合は、消費生活センターや消費者庁に相談し、該当するかどうかを確認しましょう。
特に「訪問販売」や「電話勧誘」だった場合は、8日以内であればクーリングオフができる可能性があります。
状況に応じた対応策を提示してくれるため、まずは専門機関に相談することが第一歩です。
警察に相談する
明らかな詐欺の被害に遭っている場合や、返金交渉に応じない、脅迫的な対応をされたときは警察への相談が必要です。
証拠が揃っていれば、詐欺罪として捜査が行われる可能性もあります。
被害届を提出する際には、契約書や支払い記録、やり取りのスクリーンショットなどをまとめておくとスムーズです。
悪質な業者を摘発することが、同様の被害者を減らす一助にもなります。
クレジットカード会社に相談する
情報商材の支払いをクレジットカードで行った場合、決済停止(チャージバック)の申請が可能です。
これは、正当な理由に基づき取引を無効化する制度で、詐欺被害の返金に活用されるケースがあります。
カード会社によって対応は異なりますが、早期に連絡し、必要な証拠を提出することで手続きが進みます。
返金の見込みが薄い場合でも、チャージバックによって一部金額を取り戻せることがあります。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
情報商材詐欺の被害例
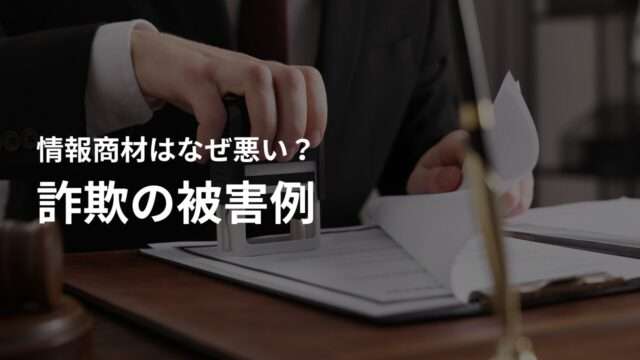
SNSを通じて「誰でも簡単に儲かる」「月収○○万円可能」などと謳う副業や投資関連の情報商材が数多く出回っています。
しかし、その多くが実態のない詐欺まがいの内容で、高額な契約や追加支払いを誘導されるケースも少なくありません。
ここでは、実際に被害にあった3つの事例をもとに、どのような手口で利用者がだまされていったのかを紹介します。
安易に儲け話に飛びつくリスクについて、あらためて考えてみましょう。
SNS広告に誘われ高額FX商材を契約、効果なく後悔
AさんはSNSで「月利50%」「誰でも稼げる」などと宣伝されていたFX情報商材に興味を持ち、無料セミナーに参加しました。
セミナーでは簡単に利益が出せると強調され、当日限定で100万円が約40万円になると言われ契約。
指定口座に振込後、教材をダウンロードし助言を受けながら実践したが、成果はでることがありませんでした。
さらに、月利100%をうたう上位コースがあると知り、ホテルの喫茶店で勧誘を受け、「本日限り」と契約を迫られ110万円を支払うことに(50万円一括・60万円はリボ払い)。
教材はSNSや動画で提供されましたが、内容は極めて一般的で、期待した効果を得ることはできませんでした。
出典:独立行政法人 国民生活センター 報道発表資料
SNSで情報商材を購入も詐欺被害、数万円の損失
SNSで「簡単に儲けられる方法」と宣伝されていた情報商材に興味を持ったBさんは、商品を購入しました。
しかし、その内容はSNSでフォロワーを増やす方法やアフィリエイトの仕組みなど、インターネット上で無料で手に入る情報ばかりでした。
さらに、「もっと稼ぐには高額な情報商材が必要」といった案内メールが次々に届き、Bさんは詐欺であることに気づきました。
返金を求めましたが返答はなく、最終的に数万円の損失を被ってしまいました。
安価な副業商材から高額契約へ誘導、約束のサポートもなく損失
SNSで「1日10万円稼げる副業」と紹介され、Cさんは興味を持ち1万円の情報商材をデビットカードで購入しました。
その後、事業者から電話相談の予約を促され、相談当日に「アクセス数を増やすツール」などを含む90万円の契約を勧められました。
高額なため数万円のコースを希望しましたが、「返金も可能」と説得され、クレジットカードで決済。
その後さらに、「作業が進まない」として約85万円の新たな契約を現金で迫られ、断れず支払いました。
命がけのサポートを謳っていたにもかかわらず実際の支援はなく、言われた通りに作業しても利益は出ず、解約・返金も拒否されました。
出典:独立行政法人 国民生活センター 報道発表資料
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
まとめ
情報商材には、知識やスキルを学ぶうえで有益なものもあります。
しかし現実には、粗悪な内容や高額請求、返金拒否などのトラブルが多発しており、購入には非常に慎重な判断が求められます。
この記事では、情報商材が「なぜ悪い」と言われるのか、その背景や具体的な手口、被害を防ぐための対策、返金の可能性について詳しく解説してきました。
注意すべき点は、以下のポイントです。
- SNSや広告による誇大な表現
- 内容と価格の不均衡
- クーリングオフの適用範囲の理解
- 返金を求めるための適切な対応先の選定
そして最も重要なのは、「少しでも不安を感じたら買わない勇気を持つこと」です。
情報に価値がある時代だからこそ、正しい選択で自分自身を守りましょう。
【情報商材詐欺の疑いがある方へ】
情報商材詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。
当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。
当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。
当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。
本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。