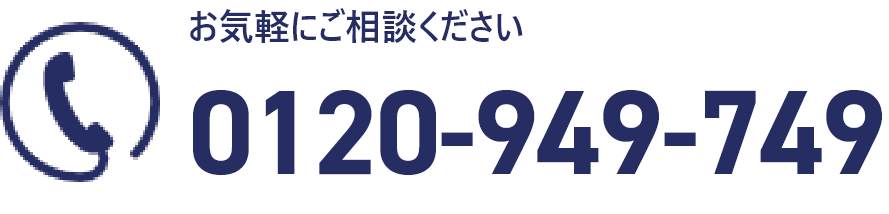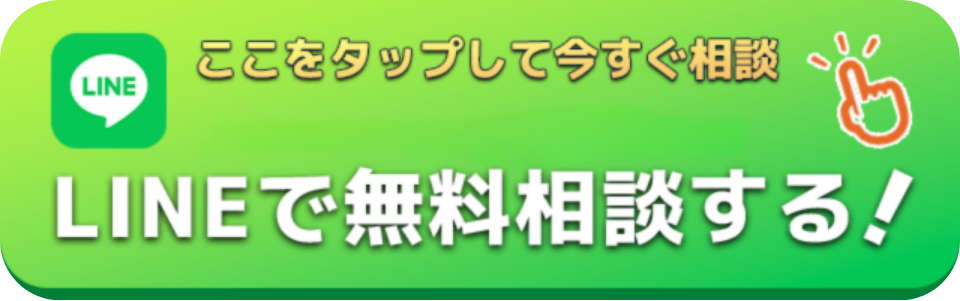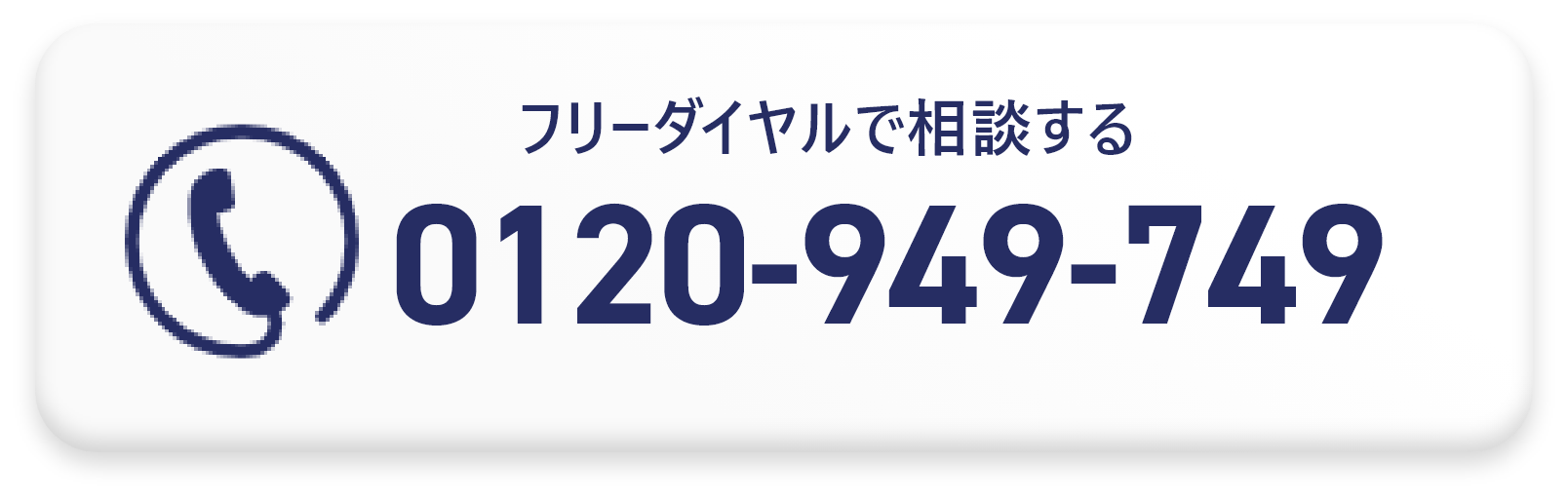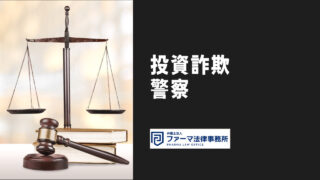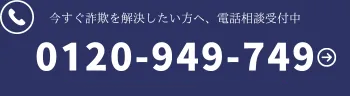仮想通貨詐欺の被害者が増加する中、対処法を知らずに泣き寝入りするケースが後を絶ちません。
本記事では、仮想通貨詐欺の典型的な手口や特徴を解説するとともに、被害に遭った際の具体的な対応策と返金可能性について専門家の視点からお伝えします。
泣き寝入りするリスクを理解し、適切な対処法を身につけることで、被害の最小化や回復につなげましょう。
【仮想通貨詐欺の疑いがある方へ】
仮想通貨詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
一体なぜ?仮想通貨詐欺で「泣き寝入り」する理由
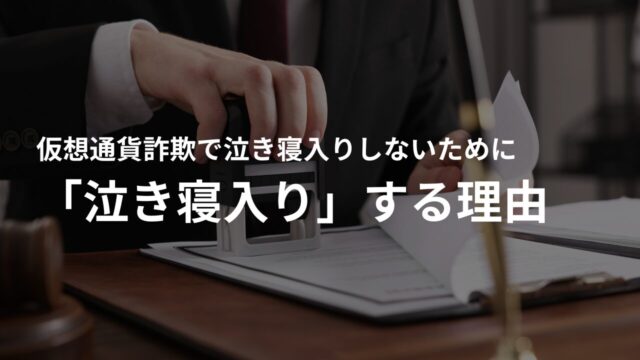
仮想通貨詐欺にあっても、多くの方が法的措置を講じず泣き寝入りしてしまいます。
その背景には、法的手続きに必要な資金不足や、詐欺師の追跡困難性、相談先の不明確さなど様々な要因が存在します。
これらの障壁を理解することで、詐欺被害に遭った際の適切な対応への第一歩となるでしょう。
法的措置に必要な資金が不足している
仮想通貨詐欺被害に遭った場合、法的措置を取るためには弁護士や司法書士への相談料や着手金が必要になります。
被害にあったばかりでお金を失っている状況で、さらに法的措置のための資金を用意するのは容易ではありません。
特に被害額が数十万円程度の場合、法的措置にかかる費用と回収できる金額を考えると、費用対効果の面で諦めてしまう方も少なくないでしょう。
初回相談が無料の法律事務所も多く存在するため、まずは費用負担なく専門家に相談することから始めるのが賢明です。
相談の結果、被害回復の見込みがあると判断されれば、着手金を支払って本格的な対応を依頼することを検討するとよいでしょう。
詐欺師に関する情報が不足しており追跡が不可能
仮想通貨詐欺では、詐欺師の身元や連絡先が不明確なケースが多く、被害者は誰に対して法的措置を取ればよいのか判断できないことがあります。
特にインターネット上での詐欺は、匿名性が高く、詐欺師が偽名や架空の連絡先を使用していることが一般的です。
仮想通貨自体も送金先の追跡が難しいため、お金の流れを把握することが困難になります。
取引所のアカウント情報やトランザクションIDなど、わずかな手掛かりでも専門家に相談することで、追跡の糸口になる可能性があります。
詐欺師の情報が限られていても、早期に専門家に相談することで詐欺師を特定する方法が見つかるかもしれません。
そもそもどこに相談していいか分からない
仮想通貨詐欺の被害に遭った場合、どこに相談すればよいのか分からず、適切な対応ができないケースも多いです。
警察、消費者センター、金融庁、弁護士、司法書士など、様々な相談先が存在しますが、どこが最適なのかが分かりにくいのが現状です。
また、仮想通貨に関する知識が不足している相談窓口もあり、適切な対応を受けられない場合もあります。
一箇所だけでなく、複数の相談先を検討しましょう。例えば法的措置を検討している場合、複数の弁護士を比較してみると良いでしょう。
消費者センターや警察への相談も被害事例の集積という意味で社会的に重要ですので、複数の窓口に相談することも検討してみましょう。
詐欺に遭ったという証拠が不十分
仮想通貨詐欺の被害を証明するための証拠が不足しているケースも、泣き寝入りの原因となります。
詐欺師とのやり取りの記録や送金履歴など、詐欺被害を裏付ける証拠がなければ、法的措置を取ることが難しくなります。
特にSNSやLINEでのやり取りが削除されていたり、詐欺サイトが閉鎖されていたりすると、証拠の収集がさらに困難になります。
取引や会話の記録は常にスクリーンショットなどで保存しておくことが重要です。
少しでも不審に感じたら、その時点から証拠を集め始めることで、後の法的措置の可能性を高めることができます。
被害から長期間経っている
仮想通貨詐欺の被害から時間が経過している場合も、泣き寝入りせざるを得ないケースが増えます。
詐欺師は被害発覚後、すぐに姿をくらますことが多く、時間が経つほど追跡が困難になります。
また、法的には詐欺の場合の損害賠償請求権の消滅時効は3年とされていますが、時間の経過とともに証拠が散逸するリスクも高まります。
被害に気づいたらすぐに行動することが、被害回復の可能性を高める重要なポイントです。
「様子を見よう」と思っている間に詐欺師の痕跡が消え、取り返しがつかなくなることもあるので注意が必要です。
海外の業者が関与する仮想通貨詐欺
海外の業者や取引所が関与する仮想通貨詐欺は、法的措置を取ることが特に困難です。
国境を越えた法的手続きは複雑で時間と費用がかかり、一般の被害者には大きな負担となります。
また、国によって法律や規制が異なるため、日本の法律で違法とされる行為が海外では合法とされる場合もあります。
海外の業者と取引する際は、事前に信頼性を十分に確認することが重要です。
万が一、海外業者による詐欺の被害に遭った場合でも、国内の専門家に相談することで何らかの対応策が見つかる可能性があります。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
泣き寝入りしないために知っておくべき!仮想通貨詐欺の典型的な特徴
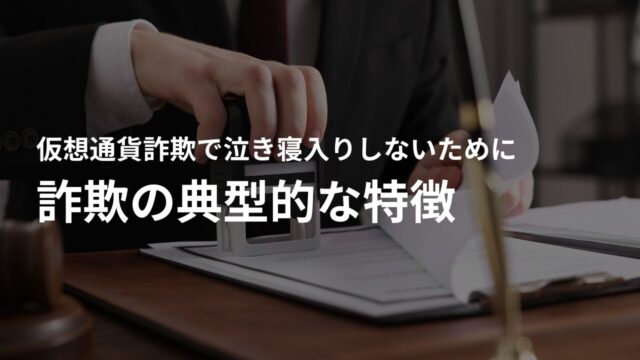
仮想通貨詐欺を未然に防ぐには、その典型的な特徴や手口を知っておくことが重要です。
詐欺師は常に新たな手口を編み出していますが、基本的なパターンを理解していれば、怪しい取引や勧誘に警戒することができます。
ここでは、仮想通貨詐欺に共通する特徴について解説します。
偽サイトへ誘導する
仮想通貨詐欺では、正規の取引所や販売サイトに似せた偽サイトへ誘導するケースが多く見られます。
これらの偽サイトは見た目が本物そっくりに作られており、一見しただけでは区別がつかないほどです。
ユーザーがログイン情報を入力すると、その情報が詐欺師に盗まれ、実際の口座から資金が引き出されてしまいます。
偽サイトの見分け方として、URLをよく確認することが重要です。正規のURLと少しだけ違う場合や、「https:」ではなく「http:」から始まるサイトは要注意です。
また、取引所のサイトにアクセスする際は、検索エンジンからではなく、ブックマークや公式アプリを利用するのが安全です。
URLがおかしい
仮想通貨詐欺サイトの多くは、本物のサイトとわずかに異なるURLを使用しています。
例えば、「coincheck.com」の代わりに「coin-check.com」や「coinchek.com」など、一文字違いや、ハイフンが入ったURLを使うことがあります。
こういった細かな違いは見落としがちですが、詐欺サイトを見分ける重要な手掛かりとなります。
URLに不審な点があるサイトでは、個人情報や送金などの重要な操作を行わないことが大切です。
少しでも違和感を感じたら、公式アプリや公式サイトからアクセスし直すことで安全を確保できます。
「高配当」「リスクゼロ」を謳うが根拠に乏しい
「絶対に儲かる」「リスクなし」「元本保証」などの謳い文句は、仮想通貨詐欺の典型的な特徴です。
投資には必ずリスクが伴うもので、仮想通貨市場は特に価格変動が激しく、「確実に儲かる」という保証はあり得ません。
このような非現実的な利益を約束する案件は、詐欺の可能性が非常に高いと考えるべきです。
投資の基本原則として、リターンが高いものはリスクも高いという点を忘れないようにしましょう。
怪しい勧誘を受けた場合は、その投資のビジネスモデルや収益源について具体的に質問し、曖昧な回答であれば関わらないことが賢明です。
新たなプロジェクト、ICOによる利益を謳う
仮想通貨詐欺では、新しい仮想通貨プロジェクトやICO(Initial Coin Offering)を利用したケースが多く見られます。
「今参加すれば安く購入でき、上場後に大きな利益が得られる」などと勧誘し、実態のない仮想通貨に投資させる手口です。
実際には上場する予定もなく、集めた資金は詐欺師のポケットに入るだけという結末になりがちです。
新規の仮想通貨プロジェクトを検討する際は、開発チームの経歴、ホワイトペーパーの内容、プロジェクトのロードマップなどを徹底的に調査しましょう。
有名な取引所への上場予定があるという話も、その取引所の公式発表で確認できない限り信用すべきではありません。
日本語に違和感がある
仮想通貨詐欺のウェブサイトやメッセージには、不自然な日本語表現が見られることが多いです。
誤字脱字が多い、文法がおかしい、機械翻訳のような不自然な表現といった特徴があります。
これは海外の詐欺グループが自動翻訳ツールなどを使って日本向けに詐欺を行っているケースが多いためです。
信頼できる企業や取引所であれば、プロの翻訳者や日本語ネイティブによる自然な文章を使用しているはずです。
日本語の表現に違和感を感じたら、それは詐欺の警告サインかもしれません。
とはいえ、近年はAIによる翻訳も発達しており、日本人と見分けがつかない可能性もあります。「カタコトの日本語ではないから」という理由だけで信用しないようにしましょう。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
仮想通貨詐欺を予防する方法は?
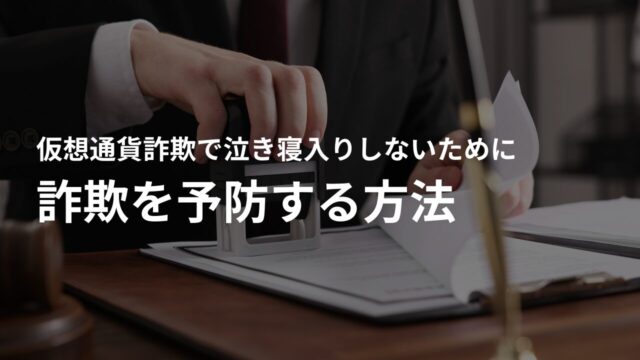
仮想通貨詐欺による被害を未然に防ぐためには、予防策を講じることが最も効果的です。
「うまい話には裏がある」という格言通り、怪しい勧誘や投資話には慎重に対応することが大切です。
ここでは、仮想通貨詐欺から身を守るための具体的な予防法について解説します。
うますぎる話には乗らない
仮想通貨詐欺を避けるための最も基本的な原則は、「うますぎる話には乗らない」ということです。
「1ヶ月で資産が2倍」「リスクなしで高利回り」などの非現実的な利益を約束する投資話は、ほぼ間違いなく詐欺です。
金融の基本原則として、高いリターンには必ず相応のリスクが伴うものであり、この原則に反する話は信用すべきではありません。
投資判断を急がされるケースも要注意です。「今だけ特別」「期間限定」などと言われて焦らされると冷静な判断ができなくなります。
投資の意思決定は常に冷静に、自分のペースで行うことが重要です。
情報の信頼性を重視する
仮想通貨取引を行う際は、信頼できる情報源からの情報を重視することが大切です。
金融庁の登録業者リスト、大手メディアの報道、公式のホワイトペーパーなど、信頼性の高い情報源を参照しましょう。
SNSやメッセージアプリでの口コミ情報は、詐欺師が作成した可能性もあるため過度に信用するのは危険です。
日本で仮想通貨取引所を利用する場合は、金融庁に登録された正規の事業者かどうかを必ず確認しましょう。
未登録の取引所を利用することは、詐欺被害のリスクを大きく高めることになります。
仮想通貨詐欺の手口を知っておく
最新の詐欺手口に関する情報をアップデートしておくことも、予防策として有効です。
詐欺師は常に新たな手口を編み出しており、警戒心を持つためには最新の手口を知っておく必要があります。
警察や金融庁、消費者センターなどが発表する注意喚起情報をチェックしておくと良いでしょう。
疑わしい勧誘を受けた場合は、インターネットで同様の手口に関する情報や被害報告がないか調べてみることも有効です。
ここからは、特に警戒すべき具体的な仮想通貨詐欺の手口について解説します。
SNSの広告等から誘導
SNSプラットフォームの広告やダイレクトメッセージを通じて怪しい投資案件に誘導する手口が増えています。
X(旧Twitter)やインスタグラム、Facebookなどで「億り人の投資法」「簡単に稼げる方法」などの広告が表示され、クリックすると詐欺サイトに誘導されるパターンです。
有名人や投資家を装った偽アカウントからの投資勧誘も、この手口の一種です。
SNSで見かける投資関連の広告やメッセージは、内容を鵜呑みにせず、必ず別の信頼できる情報源で裏付けをとることが重要です。
有名人が宣伝しているように見える場合でも、その人の公式サイトやメディアでの発言と一致しているか確認しましょう。
マッチングアプリから誘導
近年増加しているのが、マッチングアプリで知り合った人物から投資話を持ちかけられるパターンです。
典型的なケースでは、マッチングアプリで異性と知り合い、親密になった後に「自分は投資で成功している」「あなたにも教えたい」と投資話を持ちかけてきます。
これは「ロマンス詐欺」と「投資詐欺」を組み合わせた手法で、感情的なつながりを利用して警戒心を解くのが特徴です。
オンラインで知り合った相手から投資話を持ちかけられた場合は、どんなに親密な関係になっていても十分に警戒すべきです。
特に「専用の取引所やアプリを使う必要がある」と言われた場合は、高い確率で詐欺の可能性があります。

ポンジスキーム
仮想通貨投資を装ったポンジスキーム(新規投資家から集めた資金を今いる投資家への配当に回す詐欺手法)も頻繁に見られます。
初期の投資家には実際に高い配当が支払われることもあるため、「本当に儲かる」と信じ込んで多額の投資をしたり、友人や家族を勧誘したりしてしまうケースがあります。
しかし、新規投資家の資金が不足すると破綻し、最後に投資した人ほど大きな損失を被る結果となります。
「友人や知人を紹介すると報酬がもらえる」というシステムは、ポンジスキームの典型的な特徴です。
実際の運用実績やビジネスモデルが不透明な案件には手を出さない方が安全です。

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
仮想通過詐欺で泣き寝入りする前にやるべきこと8選
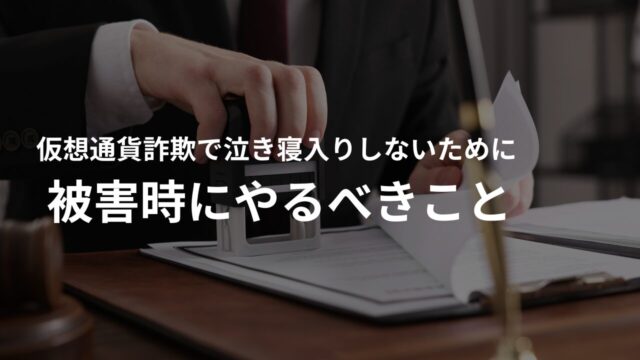
もし仮想通貨詐欺の被害に遭ってしまったと気づいた場合、泣き寝入りせずに適切な対応をとることが重要です。
被害直後の行動が、その後の被害回復の可能性を大きく左右します。
ここでは、被害に遭った際にすぐに行うべき7つの行動について解説します。
被害金額や被害に遭った日時をメモする
仮想通貨詐欺の被害に遭ったと気づいたら、まず被害金額や被害に遭った日時を正確に記録しましょう。
送金した日時、金額、仮想通貨の種類、送金時のレート(日本円換算)などを可能な限り詳細にメモしておくことが重要です。
複数回に渡って被害に遭っている場合は、それぞれの取引について記録を残しておきましょう。
記録は時系列でまとめておくと、後の法的手続きや相談の際にスムーズに説明できます。
被害の全体像を把握することで、適切な対応策を検討する手助けになります。
勧誘者や購入先、振込先の講座情報などを記録する
詐欺に関わった人物や企業、サイトの情報をできる限り記録しておきましょう。
勧誘者の名前、連絡先、SNSアカウント、仮想通貨を購入した取引所や販売サイトのURL、振込先の口座情報など、あらゆる情報が重要な証拠となります。
これらの情報は詐欺師を特定するための重要な手掛かりとなります。
詐欺サイトは発覚後すぐに閉鎖されることが多いため、気づいた時点でスクリーンショットを撮っておくことが大切です。
勧誘者のSNSアカウントも同様に、スクリーンショットなどで記録を残しておきましょう。
トランザクションID(TxID)などの取引に関する情報を保存する
仮想通貨の送金履歴は、トランザクションID(TxID)という固有の識別子で管理されています。
このTxIDがあれば、ブロックチェーン上で取引を追跡することができ、資金の流れを証明する重要な証拠となります。
送金時に表示されるTxIDや取引確認画面は必ずスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
トランザクションIDがあれば、専門家が資金の流れを追跡できる可能性が高まります。
また、取引所のアカウント情報や取引履歴なども同様に保存しておくことが重要です。
詐欺師とのやりとりを記録する
詐欺師とのすべてのコミュニケーションを証拠として保存しておきましょう。
メール、LINE、SMS、SNSのメッセージなど、あらゆるやり取りが詐欺の証拠となります。
特に、投資の利益や仕組みについての説明、送金を促す文言などは重要な証拠となるため、必ず保存してください。
メッセージのスクリーンショットは日付や時刻も含めて保存し、やり取りの流れが分かるようにしておくことが重要です。
今後も詐欺師とコンタクトを取る場合は、すべてのやり取りを記録し続けましょう。
もし相手の住所が分かれば控えておく
詐欺師や関連企業の実在の住所や所在地が分かる場合は、必ず記録しておきましょう。
会社案内、契約書、ウェブサイトのお問い合わせページなど、あらゆる情報源から住所情報を収集します。
住所が分かれば、内容証明郵便の送付や法的手続きの際に役立ちます。
住所が実在するかどうかは、Googleマップなどで確認してみるとよいでしょう。
海外の住所の場合も、できる限り正確に記録しておくことが重要です。
消費者被害の窓口に相談
仮想通貨詐欺は、消費者庁が運営する消費者ホットラインや国民生活センターなどの公的相談窓口に相談することができます。
また、組織的な詐欺被害の場合は、同じ手口で被害に遭った他の方々と情報を共有できる可能性もあり、解決への糸口が見つかることもあります。
早期の相談が被害拡大防止につながるため、「不審に感じる」ような場合は上記に相談することをおすすめします。
警察への相談
詐欺罪は刑法246条に定められている通り、10年以下の懲役が科せられる犯罪です。被害に気づいたら、すぐに最寄りの警察署に相談しましょう。
警察は詐欺被害の相談を受け付けており、被害状況や証拠に基づいて被害届を受理してくれる場合があります。
特に組織的な詐欺の場合、複数の被害者の情報が集まることで捜査が進展する可能性があります。
警察に相談する際は、これまでに収集した証拠や記録をすべて持参し、被害の経緯を時系列で説明できるよう準備しておきましょう。
警察だけでなく、消費者センターや金融庁の相談窓口に相談することも検討しましょう。
弁護士への相談
仮想通貨詐欺の被害回復には、専門的な法律知識が必要なため、弁護士への相談が有効です。
特に仮想通貨や投資詐欺に詳しい弁護士を選ぶことで、より適切なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
弁護士に相談することで、民事上の損害賠償請求など、法的手段を講じることができます。
初回相談が無料の法律事務所も多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
弁護士費用は成功報酬制を採用している事務所もあり、事前に費用体系を確認しておくとよいでしょう。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
仮想通貨詐欺からお金を取り戻せるのか?返金方法も解説
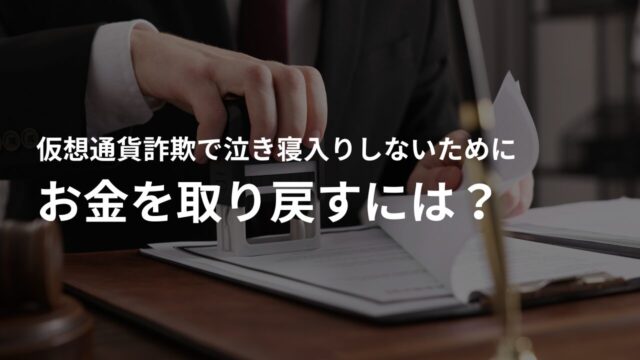
仮想通貨詐欺の被害に遭った場合、最も気になるのは「お金を取り戻せるのか」という点でしょう。
詐欺の種類や状況によって返金の可能性は大きく異なりますが、適切な対応をとることで被害回復のチャンスはあります。
ここでは、返金の可能性や難しいケースについて解説します。
弁護士・司法書士による返金対応の可能性は?
仮想通貨詐欺被害の返金には、法律の専門家に依頼するのが最も効果的です。
弁護士や司法書士は、被害者に代わって詐欺師や関連企業に内容証明郵便を送付し、返金を求める交渉を行います。
交渉が不調に終わった場合でも、民事訴訟を提起して法的に損害賠償を請求することが可能です。
弁護士・司法書士が介入することで、詐欺師に対する心理的プレッシャーとなり、返金に応じるケースも少なくありません。
仮想通貨詐欺に関する実績や経験が豊富な専門家に相談することで、返金の可能性を高めることができます。
返金が難しいケース(海外取引所・情報不明・時間経過)
一方で、返金が難しいケースもあることを理解しておく必要があります。
特に海外の取引所や業者が関与している場合、国際的な法的手続きの複雑さや高額な費用から、現実的に返金が困難なことが多いです。
また、詐欺師の情報が不明確で追跡できない場合や、被害から長期間が経過している場合も返金の可能性は低下します。
海外業者が関与する場合は追跡が困難ですが、日本国内に協力者や口座があれば追跡できる可能性があるため、専門家に相談する価値はあります。
被害額と返金請求にかかる費用のバランスも考慮して、対応を検討する必要があるでしょう。
返金を妨げる「悪質業者の巧妙な言い逃れ」
詐欺師は返金請求を受けると、様々な言い逃れを使って対応を引き延ばそうとします。
「今は相場が下がっているだけ」「もう少し待てば値上がりする」などと説明し、被害者の希望を持たせることで時間を稼ごうとするケースが多いです。
また、「システムの不具合」「一時的な出金制限」などの技術的な問題を理由に挙げる場合もあります。
詐欺師の言い逃れに惑わされず、早期に法的措置を検討することが重要です。
連絡が取れなくなる前に、できるだけ多くの証拠を集めておくことも大切です。
返金成功のために重要な「スピード」と「証拠の質」
仮想通貨詐欺からの返金成功には、迅速な行動と質の高い証拠が決め手となります。
被害に気づいた時点ですぐに対応を始めることで、詐欺師が資金を移動させたり姿をくらましたりする前に手を打つことができます。
また、やり取りの記録や送金履歴など、詳細で確実な証拠を集めることが返金請求の成功率を高めます。
詐欺の疑いを感じたら、その場で証拠を収集し、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
被害が大きいほど、専門家への相談費用を支払っても総合的にはプラスになる可能性が高まります。

仮想通貨詐欺の返金方法は?ステップ別に解説
注:上記内容は法的な一般論として正確ですが、個別の事案においては専門家への相談をお勧めします。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
仮想通貨詐欺で泣き寝入りすることで起こるリスク
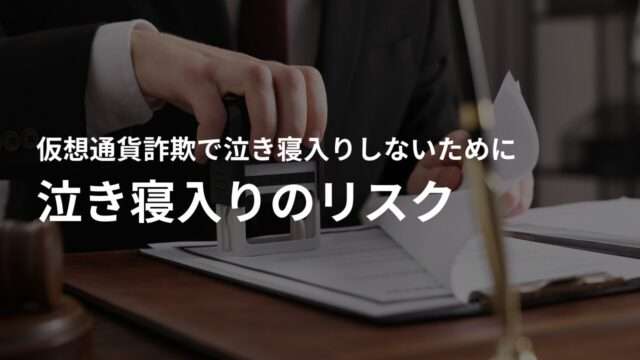
仮想通貨詐欺の被害に遭っても何もせずに泣き寝入りすることは、さらなるリスクを招く可能性があります。
経済的な損失だけでなく、個人情報の流出による二次被害のリスクも存在します。
ここでは、泣き寝入りすることで生じる様々なリスクについて解説します。
経済的損失を取り戻せない
泣き寝入りすることの最も明らかなリスクは、経済的損失を回復する機会を失うことです。
適切な対応を取らなければ、失った資金を取り戻すチャンスはゼロになってしまいます。
特に被害額が大きい場合、その損失が生活や将来計画に大きな影響を与える可能性があります。
また、法的措置を取ることで、将来的な税金控除の対象となる可能性もあります。
個人情報の流出
仮想通貨詐欺では、投資や口座開設の過程で個人情報を提供させられることが多いです。
詐欺師はこれらの個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、身分証のコピーなど)を悪用する可能性があります。
泣き寝入りして何も対策を講じなければ、個人情報の流出リスクに無防備なままとなります。
必要に応じて、本人確認書類を再発行するなどの措置も検討しましょう。
二次被害に遭うリスク
仮想通貨詐欺の被害者は、二次被害のターゲットになりやすい傾向があります。
詐欺師は被害者リストを共有することがあり、一度詐欺に引っかかった人は「カモリスト」として別の詐欺師から狙われる可能性があります。
特に「取り戻し詐欺」(最初の詐欺で失った資金を取り戻すと装い、さらにお金をだまし取る詐欺)の標的になりやすいです。
詐欺被害に関する相談や対応は、二次被害の防止にもつながります。
仮想通貨詐欺に関するよくある質問
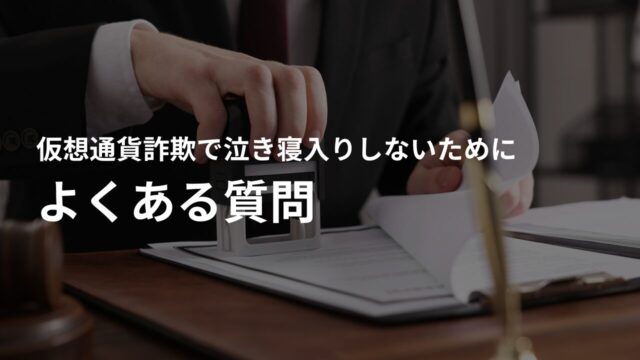
仮想通貨詐欺の被害に遭った方々からよく寄せられる質問について、専門家の視点から回答します。
少額の被害や海外業者の案件、証拠が不十分なケースなど、様々な状況に応じた対応策を解説します。
これらの情報が、被害に遭われた方々の参考になれば幸いです。
仮想通貨詐欺に遭ったけど、少額でも相談できる?
少額の被害でも相談は可能ですが、費用対効果を考慮する必要があります。
弁護士や司法書士に依頼する場合、相談料や着手金、成功報酬などの費用がかかりますので、被害額がそれらの費用を下回ると実質的な回復が難しくなります。
ただし、消費者センターや警察への相談は無料なので、被害額に関わらず相談することをおすすめします。
無料相談を実施している法律事務所も多いので、まずは相談してみることで費用や回収可能性について判断材料を得ることができます。
また、同様の手口による被害が多発している場合、少額でも被害届を出すことで捜査が進展する可能性があります。
相手が海外業者の場合、返金の可能性はある?
海外業者による詐欺は、返金のハードルが高いのが現実です。
国際的な法的手続きには多額の費用と時間がかかり、結果的に費用倒れになるリスクが高いため、現実的には難しいケースが多いです。
ただし、海外業者でも日本国内に協力者や口座を持っている場合は、追跡できる可能性があります。
海外業者との取引記録や連絡先情報などは保存しておき、専門家に相談することで可能性を探ることができます。
国際的な詐欺の場合、複数国の捜査機関が連携して対応するケースもあるため、情報提供の意味でも被害届を出しておくことは意味があります。
サイトやLINEが削除されていても対応できる?
詐欺サイトやLINEアカウントが削除されていても、他の証拠があれば対応できる可能性はあります。
重要なのは、送金の記録や取引履歴など、客観的に詐欺被害を証明できる証拠です。
このような場合、事前にスクリーンショットを取っておくことが非常に重要になります。
インターネットアーカイブ(Wayback Machine)などのサービスで、削除されたウェブサイトの過去のバージョンを確認できる場合もあります。
\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
まとめ
仮想通貨詐欺は手口が巧妙化し、被害が拡大していますが、適切な知識と対応で被害を防いだり最小化したりすることが可能です。
詐欺の典型的な特徴を把握し、怪しい投資話には警戒心を持って接することが予防の第一歩となります。
万が一被害に遭ってしまった場合も、証拠を収集し、速やかに専門家に相談することで、泣き寝入りせずに対処できる可能性があります。
特に海外業者が関与するケースや長期間経過した案件は難しいものの、諦める前に専門家に相談することをおすすめします。
また、泣き寝入りすることで二次被害のリスクが高まる点も忘れてはいけません。個人情報の保護や同様の手口による再被害を防ぐためにも、適切な対応を取ることが重要です。
最後に…仮想通貨投資自体は魅力的な選択肢ですが、「うますぎる話には裏がある」という原則を常に念頭に置き、信頼できる業者と慎重に取引を行うようにしましょう。
【仮想通貨詐欺の疑いがある方へ】
仮想通貨詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。
ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。
詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。
▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で今すぐアドバイスをもらう/
※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。
※個人情報を不正利用することは一切ありません。
こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。
当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。
当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。
当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。
本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。